
瀬尾夏美
Natsumi Seo
旅するからだ:ことばと絵をつくる
大津波のあと、岩手県沿岸の陸前高田というまちに暮らすようになりました。私はそこで日々働きながら、見聞きさせてもらうさまざまを誰かに渡したいと考えて、絵や文章をつくっていました。私は大津波も見ていないし、以前のまちの姿を知っている訳でもありません。ただ歩いて辺りを眺め、そこに居る人に話を聞き、私自身がかろうじて見えたもの・聞けたことを形にしていくのみです。だから、何かを精確におこすことは出来ません。けれど、わからないからこそ生まれるイメージのブレのなかに、受け手の居場所をつくることが出来るのかもしれない、とも思うのです。作家の身体は旅人である時にこそ機能するのではないか、そんな問いが私のなかにあります。たとえば、そこに暮らしながらも旅人であるということ。一時的にそこに居合わせて、誰かを看取ること。うつくしい風景をうつくしいと言い切ること。この場所では、実際にさまざまな土地を訪れながら考えた旅についてのあれこれを書いていきたいと思います。
02 山の終戦を訪ねる
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/single-story.php on line 49
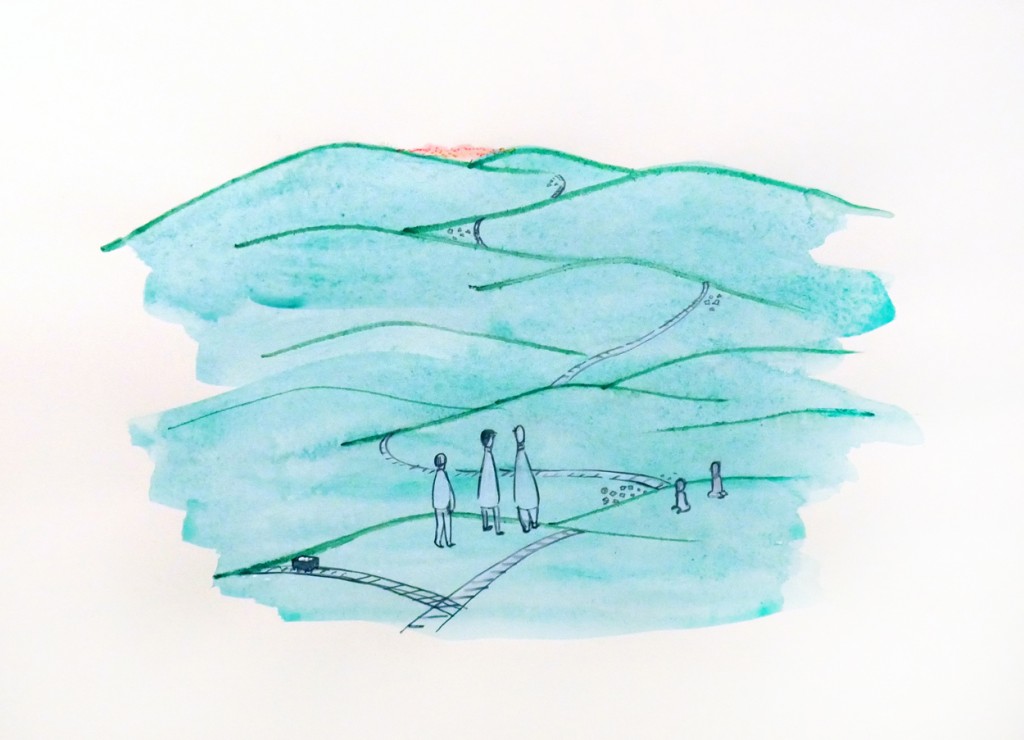
遠い火
まだここ数ヶ月のことだけれど、終戦の前後の生活について、おじいさんおばあさんに話を聞いている。なぜその頃のことについて話を聞き始めたのかと言えば、あるおじいさんが「話したい」と言ってくれたからである。彼は、宮城県の山間地、伊具郡丸森町の人であった。彼に、なぜ話したかったのかと問うと、
「俺が今にいねぐなるとす、戦死した兄貴のごどを知っでる人が誰もいねぐねってすまうがらねゎ。それが悔すぃ。」と言う。
死者について語る人に、津波のあとの陸前高田で幾人も出会った。語りとは、今は存在しない人間を別の誰かのなかにもう一度生きさせるような行為、あるいはそのような願いかもしれない、と思う。亡くなったその人を記憶する人が誰ひとりいなくなったとき、その人はもう一度死んでしまう。2度死なせることを「せづねぇ(切ない)」と感じ、語ることを諦めない人たちがいる。
長い時間のなかで幾度となく思い、語ってきたからだろうか。おじいさんはまるで、70数年前のあのときに身体ごと戻り、目の前にあるものを描写していくかのように語る。少年だったあるときが、ガキ大将であったお兄さんの姿が、その場所に確かにあった風景が、はっきりと立ち現れてくる。あまりにもあざやかな記憶の地点が、そこにある。
このような地点は、大きな出来事の周辺に出来るのかもしれない。宮城の地で40余年も民話を採訪し続けている方が、「大きな悲しみや苦しみ…抱えきれないような出来事からは、きっと物語の種が生まれるだろう」と語っておられたことを思い出す。大津波のあと、波に攫われてがらんどうのようになった土地を見たとき、ここから何かが生まれるのではないか、という直感があった。大きな喪失のあとには、その引き換えのようにして物語が生まれるのかもしれない。私がいまおじいさんから聞かせてもらっているものは、そういったものの一部なのではないか。70数年前の出来事について、聞かれることを待っている無数の物語が、まだ誰かの身体のなかにあるかもしれない。もしくは、未だ物語にすらなっていない断片が、身体のなかに渦巻いている人だっているかもしれない。
「俺が今にいねぐなるとす、戦死した兄貴のごどを知っでる人が誰もいねぐねってすまうがらねゎ。それが悔すぃ。」と言う。
死者について語る人に、津波のあとの陸前高田で幾人も出会った。語りとは、今は存在しない人間を別の誰かのなかにもう一度生きさせるような行為、あるいはそのような願いかもしれない、と思う。亡くなったその人を記憶する人が誰ひとりいなくなったとき、その人はもう一度死んでしまう。2度死なせることを「せづねぇ(切ない)」と感じ、語ることを諦めない人たちがいる。
長い時間のなかで幾度となく思い、語ってきたからだろうか。おじいさんはまるで、70数年前のあのときに身体ごと戻り、目の前にあるものを描写していくかのように語る。少年だったあるときが、ガキ大将であったお兄さんの姿が、その場所に確かにあった風景が、はっきりと立ち現れてくる。あまりにもあざやかな記憶の地点が、そこにある。
このような地点は、大きな出来事の周辺に出来るのかもしれない。宮城の地で40余年も民話を採訪し続けている方が、「大きな悲しみや苦しみ…抱えきれないような出来事からは、きっと物語の種が生まれるだろう」と語っておられたことを思い出す。大津波のあと、波に攫われてがらんどうのようになった土地を見たとき、ここから何かが生まれるのではないか、という直感があった。大きな喪失のあとには、その引き換えのようにして物語が生まれるのかもしれない。私がいまおじいさんから聞かせてもらっているものは、そういったものの一部なのではないか。70数年前の出来事について、聞かれることを待っている無数の物語が、まだ誰かの身体のなかにあるかもしれない。もしくは、未だ物語にすらなっていない断片が、身体のなかに渦巻いている人だっているかもしれない。
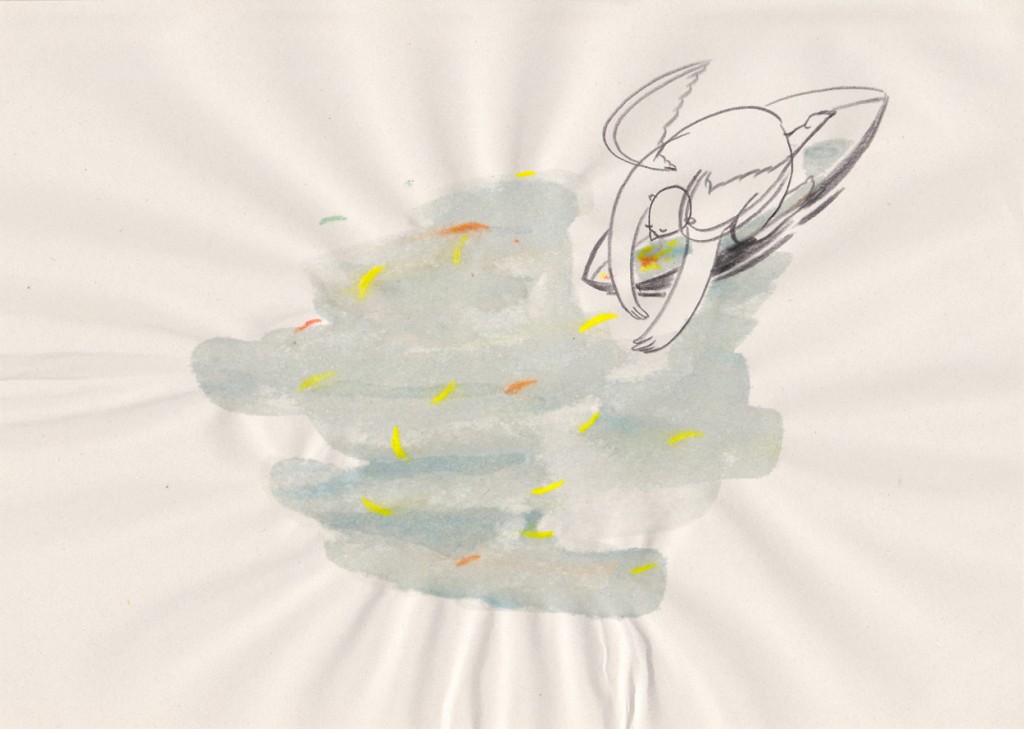
すべてをひろう
とにもかくにも偶然ではあるが、私は戦争についての語りを、東北の山奥から聞き始めることになった。山奥での戦争体験は、とても静かなものが多い。直接戦地になることはなかったから、生活そのものは淡々としている。戦争は山をいくつも越えたまちや海で繰り広げられているらしいが、自分の目で火を見ることはなかった、と彼らは言う。それでも確かに「戦争の渦中に居たのだ」ということが、戦争が終わったあとに、時間をかけて自覚されていったようだ。その事実が・戦火との距離の遠さそのものが、日本の地方都市で身の危険も感じずに暮らしている私が、70数年前の戦争を感じるうえで、とても必要なもののように思えた。当時抱えられていた戦火との空間的距離が、私が抱えているどうしようもない時間的距離と、それに伴う想像力の届かなさを、ゆるやかに肯定してくれるようだった。ひとりよがりかもしれないけれど、終戦の語りを聞くために、私は山へと歩き始めることにした。
山を訪ねては、お茶飲み話みたいにして、おじいさんおばあさんに話を聞く。いま私が話を聞いている人のほとんどは70代から80代であるから、当時は子どもだった人たちである。宮城県だったり岩手県だったりと、それぞれに点在する村であるけれど、共通するような話に幾度も出会った。
例えばお別れと迎え入れの儀式の光景、その場所。その多くは駅やバス停であった。出征していく村の男たちの見送りに、学校からその場所へと通った毎日。万歳をして、声を高くあげて、汽車やバスに乗って消えていく人たちをうっとりと見ていた、という人もあった。そしてその場所は、戦死者の英霊(その多くは遺骨そのものでなく、棒切れや本人の写真の断片であったそうだ)を迎え入れる場所にもなる。盛大に迎え入れられる英霊たちをうらやましいと感じていたという少年少女たち。おじいさんおばあさんに淡々と語られることで、当時の軍国少年少女たちが、目の前の彼らと確かに地続きであるということを、すこしずつ実感するようだった。
お話を聞いたあと時間があれば、お別れと迎え入れのその場所に連れて行ってもらった。風景は70年の時を経て、確かに変わっている。けれど、必ずどこかにかつての姿の片鱗を抱えている。思い出して話すという経験によって、彼らの目は、風景からそれを探すようになる。
「ああ、ここだここだ、確かに残っていだったねゎ。」
それを見つけては、彼らは懐かしそうに目を細めていた。
山を訪ねては、お茶飲み話みたいにして、おじいさんおばあさんに話を聞く。いま私が話を聞いている人のほとんどは70代から80代であるから、当時は子どもだった人たちである。宮城県だったり岩手県だったりと、それぞれに点在する村であるけれど、共通するような話に幾度も出会った。
例えばお別れと迎え入れの儀式の光景、その場所。その多くは駅やバス停であった。出征していく村の男たちの見送りに、学校からその場所へと通った毎日。万歳をして、声を高くあげて、汽車やバスに乗って消えていく人たちをうっとりと見ていた、という人もあった。そしてその場所は、戦死者の英霊(その多くは遺骨そのものでなく、棒切れや本人の写真の断片であったそうだ)を迎え入れる場所にもなる。盛大に迎え入れられる英霊たちをうらやましいと感じていたという少年少女たち。おじいさんおばあさんに淡々と語られることで、当時の軍国少年少女たちが、目の前の彼らと確かに地続きであるということを、すこしずつ実感するようだった。
お話を聞いたあと時間があれば、お別れと迎え入れのその場所に連れて行ってもらった。風景は70年の時を経て、確かに変わっている。けれど、必ずどこかにかつての姿の片鱗を抱えている。思い出して話すという経験によって、彼らの目は、風景からそれを探すようになる。
「ああ、ここだここだ、確かに残っていだったねゎ。」
それを見つけては、彼らは懐かしそうに目を細めていた。

宮城県伊具郡丸森町後屋敷
もうひとつ記しておきたいことがある。それは、彼らは幼少期に体験したそのことを、70数年の間にさまざまな立場に立って、繰り返し体験し直しているということだ。自分が母親になったとき、教師になったとき、孫を持ったとき。年を重ねるごとに、あのときの地点に立ち返り、あの人はどう思っていたのだろう、ということを考える。例えば、出征する兄の姿を見ながら泣いている母親を、軍国少女だった自分が叱責した、というエピソード。その後ガラリと価値観が変わった社会で思春期を過ごし、自分が母親になったとき、改めて、子を戦地にやる母親の気持ちを思う。それは、当時の自分のふるまいを全否定するのとも、母親への怒りがすべて消えるのとも違う。あのときを抱えながら、微妙に位置をずらしながら、幾度も経験し直し、そのうえでいま、語ってくれている。
「戦後、とてつもない価値観の変化をどのように受け止めましたか?」と訪ねたとき、彼女はこう答えている。
「人間は思うよりもたくますぃもんだ、というごどさ。昨日までのことが全て嘘だどなって世界が変わっても、それに合わせるもんなのさ。何よりかにより、生きていぐこと、だから。思想どか価値よりも、生ぎるごどがあるからねゎ。」
「戦後、とてつもない価値観の変化をどのように受け止めましたか?」と訪ねたとき、彼女はこう答えている。
「人間は思うよりもたくますぃもんだ、というごどさ。昨日までのことが全て嘘だどなって世界が変わっても、それに合わせるもんなのさ。何よりかにより、生きていぐこと、だから。思想どか価値よりも、生ぎるごどがあるからねゎ。」

かがむ子どもら
語りを聞きながら常に忘れたくないと思うのは、私が聞くことが出来るのは、70数年の間、彼らが出来事に向き合い反芻し続けるなかで、編集してきた語りであるということだ。ある物語のかけらのようになって現れるそれらにとって、事実であるか、誰のものであるかということは本当の問題ではなくて、彼らが何を語り伝えようとしてきたのか、ということに、その体験の本質があるのではないか。語り継ぐこと、物語になることとは、むしろ、本質があらわになっていくことなのではないか。
同時に、語りのなかには、政治的な主張やメッセージと物語が混同されている場合が時々あり、それは注意深く聞きたいとも思う。そこで私は、彼らの語りに導かれるようにして、私自身がその体験までなるべく精確に立ち戻り、自分の身体で70数年を歩いて語りなおす、という方法を試みようと思っている。ある体験の本質をもう一度咀嚼し、あらためて語りだすために。
最後に、岩手県遠野市のあるおじいさんが、ぽつりと呟いたことばを記したい。
「オレには戦争のなかった人生なんてのは成り立たねぃがらす、戦争がまるでなかったようにするのは、自分の人生そのものを否定するごどにもなるんだよ。だがらオレは語らねばなんねいのさ。語るっづごとは、とっても大切なんだよ。ひとりの経験はひとりの問題でねくて、過去の人と未来の人のものでもあるのさ。この世を生ぎでるっづごどは、そういうごどなのさ。ひとりじゃねんだよ。」
ひとつひとつの粒としての命が抱えている責任のようなものと、ひとりじゃないということのどうしようもないあたたかさに、どこかほっとする。
私は、1945年の前後のあのときを、これから幾度も訪ねたいと思っている。
同時に、語りのなかには、政治的な主張やメッセージと物語が混同されている場合が時々あり、それは注意深く聞きたいとも思う。そこで私は、彼らの語りに導かれるようにして、私自身がその体験までなるべく精確に立ち戻り、自分の身体で70数年を歩いて語りなおす、という方法を試みようと思っている。ある体験の本質をもう一度咀嚼し、あらためて語りだすために。
最後に、岩手県遠野市のあるおじいさんが、ぽつりと呟いたことばを記したい。
「オレには戦争のなかった人生なんてのは成り立たねぃがらす、戦争がまるでなかったようにするのは、自分の人生そのものを否定するごどにもなるんだよ。だがらオレは語らねばなんねいのさ。語るっづごとは、とっても大切なんだよ。ひとりの経験はひとりの問題でねくて、過去の人と未来の人のものでもあるのさ。この世を生ぎでるっづごどは、そういうごどなのさ。ひとりじゃねんだよ。」
ひとつひとつの粒としての命が抱えている責任のようなものと、ひとりじゃないということのどうしようもないあたたかさに、どこかほっとする。
私は、1945年の前後のあのときを、これから幾度も訪ねたいと思っている。

青い山に入る
記事一覧
-
2020-summer-story
02│8月12日 台湾 -
2020-summer-story
01│8月5日 東京 -
2020-summer-story
00│公開予定 -
町田恵美
01│MAX PLAN 1970-1979 -
港千尋
02│瞬間建築 -
港千尋
01│長い橋 -
関川歩
01│南方以南 the Hidden South -
呂孟恂
00│プロフィール -
町田恵美
00│プロフィール -
関川歩
00│プロフィール -
港千尋
00│プロフィール -
瀬尾夏美
05│ふるさと -
ぬかつくるとこ
05│上木戸工作室 -
辻田美穂子
05│BRIDGE STORY05 -
辻田美穂子
04│BRIDGE STORY04 -
ぬかつくるとこ
04│コイケノオイケ -
瀬尾夏美
04│架空のまち|誰かに旅をしてもらう -
ぬかつくるとこ
03│しょうへいくんのプラバン工場 -
辻田美穂子
03│BRIDGE STORY3 -
瀬尾夏美
03│なくなったまちを訪ねて -
ぬかつくるとこ
02│とだのま -
辻田美穂子
02│BRIDGE STORY02 -
02│掘る形 -
瀬尾夏美
02│山の終戦を訪ねる -
キオ・グリフィス
01│文聞録~其の一 -
辻田美穂子
01│BRIDGE STORY01 -
ぬかつくるとこ
01│「ぬか つくるとこ」とは -
瀬尾夏美
01│陸前高田にて -
01│The Color of Oil -
瀬尾夏美
00│プロフィール -
00│プロフィール -
00│プロフィール -
キオ・グリフィス
00│プロフィール -
辻田美穂子
00│プロフィール -
ぬかつくるとこ
00│プロフィール -
ムーニー・スザンヌ
05│レジリエント・アーティスト -
齋藤彰英
05│《移動すること》構造線と塩の道 ⑤ -
大谷悠
05│現代都市のアジールと「あそび」のクオリティ -
大谷悠
04│都市の「あそび」に集まるひとたち——「日本の家」となかまたち -
舩木翔平
05│新しい日常を創り出すこと -
舩木翔平
04│野菜たちの作り方 -
原亜由美
05│記憶の居場所 -
仲宗根香織
05│小舟で漕いで行く -
太田エマ
04│#IAmaMigrant -
江上賢一郎
05│『流転しつつ根をはること -マレーシア、インドネシアの芸術・文化実践- 』 -
齋藤彰英
04│《移動すること》構造線と塩の道 ④ -
ムーニー・スザンヌ
04│猫の生活:下、上、間、後ろ、向こう -
太田エマ
03│70代以上の女性:どうやって働いてきたのでしょうか? -
江上賢一郎
04│都市の瓦礫から文化をつくる。(韓国) -
仲宗根香織
04│宇宙につながる歴史、光、写真 -
原亜由美
04│リトアニアとハワイ -
大谷悠
03│「公共空間」で「あそぶ」— 小倉城を攻め落とした話 -
ムーニー・スザンヌ
03│都市発展のオルタナティブ・タイムライン -
齋藤彰英
03│《移動すること》構造線と塩の道 ③ -
舩木翔平
03│畑の中の小さなお店から始まる出来事 -
江上賢一郎
03│台南の家族たち -
仲宗根香織
03│傷の想像力 -
原亜由美
03│照らされること -
ムーニー・スザンヌ
02│包含し、守り、分ける、壁 -
齋藤彰英
02│《移動すること》構造線と塩の道 ② -
大谷悠
02│産業遺産を「アート」で「あそぶ」— ドイツの衰退工業都市に「パラダイス」をつくった話 -
舩木翔平
02│街にヤギ -
太田エマ
02│アートとプレカリアート¹ -
原亜由美
02│土地と向き合う -
江上賢一郎
02│Alternative Asia 香港編(後編) -
仲宗根香織
02│生まれ変わる街を想像する力 -
齋藤彰英
01│《移動すること》構造線と塩の道 ① -
大谷悠
01│「空き家」と「あそび」— ライプツィヒ「日本の家」 -
舩木翔平
01│ニュータウンに残された奇跡の農村風景 -
ムーニー・スザンヌ
01│場所から場所へ移動する / As We Travel from Point to Point -
原亜由美
01│夏と記憶の欠片 -
太田エマ
01│パブリックと領域
場所を持つことはパブリックを不可能にするか? -
江上賢一郎
01│Alternative Asia 香港編(前編) -
仲宗根香織
01│秘密のない風景 -
ムーニー・スザンヌ
00│プロフィール -
舩木翔平
00│プロフィール -
大谷悠
00│プロフィール -
齋藤彰英
00│プロフィール -
仲宗根香織
00│プロフィール -
原亜由美
00│プロフィール -
太田エマ
00│プロフィール -
江上賢一郎
00│プロフィール
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22
