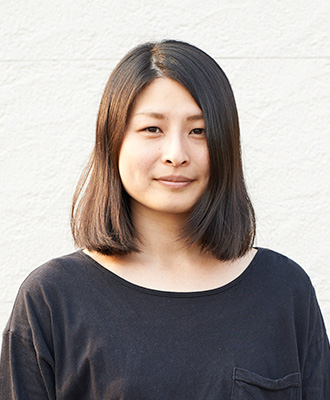
辻田美穂子
Mihoko Tsujita
故郷は文字通り、誰しもが持っている唯一無二の場所です。しかしそれは揺らぐことのない絶対的な存在なのでしょうか。16歳から19歳まで過ごしたオーストラリアでは自分が日本人であることを根本から否定されるような出来事がありました。生まれた大阪という土地で染み付いた風習を恥じ、土地柄はできるだけ隠して過ごしました。一方で、海の向こうから届く祖母からの手紙には、訪れることのできない遠い故郷の思い出が、大事に綴られていました。
他人と共有したい素晴らしい景色も、できれば隠しておきたい事柄も、写真として切り取られた「今」は、在りのままとして等価に写ります。たったひとつの場所を想い続けるということ。根を下ろさずに土地を移ろい暮らすとういうこと。2013年に北海道に移り住んで以来、これらの境界はだんだんと曖昧になりつつあります。日々の暮らしにカメラを持ち込み、全てを一旦並列にすることで、わからなさを解きほぐしていきたいと考えています。
他人と共有したい素晴らしい景色も、できれば隠しておきたい事柄も、写真として切り取られた「今」は、在りのままとして等価に写ります。たったひとつの場所を想い続けるということ。根を下ろさずに土地を移ろい暮らすとういうこと。2013年に北海道に移り住んで以来、これらの境界はだんだんと曖昧になりつつあります。日々の暮らしにカメラを持ち込み、全てを一旦並列にすることで、わからなさを解きほぐしていきたいと考えています。
02 BRIDGE STORY02
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/single-story.php on line 49

2010年8月、祖母と共にサハリンへ渡った。祖母にとっては終戦後の引き揚げ以来、62年ぶりの帰郷だった。当初は私一人で日本からの墓参団について行くつもりだった。「ロスケは何しよるかわかれへん」二十歳そこそこの私は、恐怖よりも好奇心の方が強く、祖母の制止は気にもとめず黙々と準備を進めていた。すると、ある日突然「私も行こうかな」と祖母が言い出したのである。あれだけロシア人に対して否定的なことを言っていた祖母の気の変わりようが少し気になったが、それ以前にまさか一緒に行けるとは思ってもいなかったので、とても嬉しかった。
サハリンへ渡る前日、初めて北海道最北の街、稚内を訪れた。8月というのに涼しく、乾いた空気に漂うバラに似た香りが心地よかった。港付近を散歩していると、それがハマナスだということがわかった。一緒に歩いていた祖母がその実にまじまじと見入るように手を触れた。その日はよく晴れていて、防波堤からもくっきりと43キロ先にあるサハリンの島影が見えたが、それがどのくらい遠いのかも近いのかもわからなかった。翌朝、国際ターミナルより船に乗り込んだ。乗客は300名定員のところ、私たち墓参団と、大きな荷物を持ったロシア人を合わせて40名ほどだった。航行を始めてしばらくすると、船内に国境を越えたというアナウンスが流れる。甲板へ出てみると、濃い霧で前が見えず、水分を含んだ空気は重い。2000トンの船は、いつの間にか群青色になっていた海原を北へ北へと荒々しく掻き分けて進んだ。
5時間半の航海を終え、やっと辿り着いたサハリンはすでに夕方だった。その日は街までバスで1時間ほど走り、早めの夕食を終えて翌日に備えた。祖母の生まれ育った恵須取(えすとる、現ウグレゴルスク)までは州都の豊原(現ユジノサハリンスク)からバスで更に6時間ほど北へ行ったところにある。アスファルトが敷かれてあるのはユジノから1時間ほどで、それからは未舗装の悪路が続く。北には炭山もあり、採掘された石炭を運ぶトラックの往来が激しく、それらが巻き上げる粉塵はすれ違い様にどこからか車内へ侵入し、土埃の舞う車中では息をするのもやっとだった。途中昼休憩にと立ち寄ったカフェではトイレが流れず、外からバケツリレーで水を運び片付けた。何時間も続く車の振動と土埃で体はどっと疲れていて、大量に盛られたマッシュポテトには手をつけられなかった。そこからあと2時間ほど走ると目的地である恵須取だが、疲労と緊張でいつの間にか眠ってしまった。
「煙突や!」と言う祖母の声が遠くから聞こえてきた。はっとして起きると、バスの最後尾に座っていた祖母が座席につかまりながら、ガタガタと揺れる車内をよろめきながら私のいる前方へ移動してくるところだった。「煙突や!王子の煙突や!」私をゆすり起こして叫ぶ祖母の視線の先には、遠くからでもはっきりと4本の煙突がそびえ立っているのが見えた。1929年(昭和4年)に曾祖父母は樺太へ渡った。広大な森林のおかげで豊富にある木材、四方を囲む海からとれる鮭や鰊などの海産物、さらには立派な炭山がいくつも見つかり、三菱や三井といった財閥が次々と炭鉱を開いた。その豊富な資源に着目した王子製紙が、現地の製紙工場を吸収合併しながら、大正から戦前にかけて樺太に9つの工場を築いた。そのうちのひとつ、恵須取工場に就職した曾祖父は、渡航から2年後、祖母を授かった。そんな曾祖父が勤めた王子の煙突は、62年間、同じ姿でずっとそこに立っていた。「ああ、戻って来たんだ」煙突を見た祖母があとで私にぽつりと言ったその一言が忘れられない。
それから4日間ほど、他の参加者と共に思い出の地を巡った。生家が建っていた場所、通った小学校、墓地、病院跡。同じ建物は残っていなかったが、川や山の位置は変わらないので、地形から判別して、当時のことを思ったに違いない。ひとつひとつ何かを確認するように、祖母の顔つきは日を追うごとに確固たるものへと変わっていった。
恵須取を去る日、バスの中から4本の煙突をじいっと祖母は見つめていた。眉頭は寄り、目尻が垂れ下がる。その目に涙はなかったが、ものすごく愛おしいものを見るように、遠ざかる街と煙突をいつまでも見つめ続けた。祖母の顔は清々しく、私はその表情にシャッターを切らずにはいられなかった。気がつくと、カメラの背面が涙で濡れていた。私の知らない祖母の表情。自分の暮らした家の跡だけではなく、さらにその先の何かに見入っていた視線。
私は見たかった。その時、祖母には見えて私に見えなかったものを。それから6回、いつか見えるのではと、その想いにすがるようにサハリンへ通い続けた。
2016年、8月も終わりに差し掛かったある日、サハリンへ電話をかけた。自分の携帯電話から、ウグレゴルスクに住むナージャという女性にだ。ダイヤルアシストで自動的に海外の電話に転送される。初めてサハリンを訪れた6年前からすると、随分簡単に連絡がとれるようになった。10回ほどの呼び出し音のあとに、「アロー?」と低い女性の声。「ナージャ?」「ダー(イエス)」「ミホコだよ」「ダー、カクジュラー?(元気か?)」元気だ、10月にサハリンに行くよ、というと「ハラショー、ハラショー(わかったよ)」とナージャ。昨年ナージャが札幌を訪れて以来1年ぶりの会話だったが、久しぶりの連絡に特段驚くわけでもなく、淡々と話し続けている。私はあまりロシア語が話せないので、知っている単語を並べ、用件を伝える。ナージャも同じく、片言の日本語を返してくれる。たった5分ほどの短い電話だったが、ウグレゴルスクへ着く日は伝わったようだ。「エストル、着く、テレフォン、ナージャかける」バス停に着いたら電話をよこせと言っている。そこにナージャがいなくても、昼間に着くバスは1本しかないので、歩いているうちにどこかで出会うだろうと、あまり心配もせず「パカパカー(またね)」と電話を終えた。2年ぶりのサハリン渡航まで1か月をきった。
サハリンへ渡る前日、初めて北海道最北の街、稚内を訪れた。8月というのに涼しく、乾いた空気に漂うバラに似た香りが心地よかった。港付近を散歩していると、それがハマナスだということがわかった。一緒に歩いていた祖母がその実にまじまじと見入るように手を触れた。その日はよく晴れていて、防波堤からもくっきりと43キロ先にあるサハリンの島影が見えたが、それがどのくらい遠いのかも近いのかもわからなかった。翌朝、国際ターミナルより船に乗り込んだ。乗客は300名定員のところ、私たち墓参団と、大きな荷物を持ったロシア人を合わせて40名ほどだった。航行を始めてしばらくすると、船内に国境を越えたというアナウンスが流れる。甲板へ出てみると、濃い霧で前が見えず、水分を含んだ空気は重い。2000トンの船は、いつの間にか群青色になっていた海原を北へ北へと荒々しく掻き分けて進んだ。
5時間半の航海を終え、やっと辿り着いたサハリンはすでに夕方だった。その日は街までバスで1時間ほど走り、早めの夕食を終えて翌日に備えた。祖母の生まれ育った恵須取(えすとる、現ウグレゴルスク)までは州都の豊原(現ユジノサハリンスク)からバスで更に6時間ほど北へ行ったところにある。アスファルトが敷かれてあるのはユジノから1時間ほどで、それからは未舗装の悪路が続く。北には炭山もあり、採掘された石炭を運ぶトラックの往来が激しく、それらが巻き上げる粉塵はすれ違い様にどこからか車内へ侵入し、土埃の舞う車中では息をするのもやっとだった。途中昼休憩にと立ち寄ったカフェではトイレが流れず、外からバケツリレーで水を運び片付けた。何時間も続く車の振動と土埃で体はどっと疲れていて、大量に盛られたマッシュポテトには手をつけられなかった。そこからあと2時間ほど走ると目的地である恵須取だが、疲労と緊張でいつの間にか眠ってしまった。
「煙突や!」と言う祖母の声が遠くから聞こえてきた。はっとして起きると、バスの最後尾に座っていた祖母が座席につかまりながら、ガタガタと揺れる車内をよろめきながら私のいる前方へ移動してくるところだった。「煙突や!王子の煙突や!」私をゆすり起こして叫ぶ祖母の視線の先には、遠くからでもはっきりと4本の煙突がそびえ立っているのが見えた。1929年(昭和4年)に曾祖父母は樺太へ渡った。広大な森林のおかげで豊富にある木材、四方を囲む海からとれる鮭や鰊などの海産物、さらには立派な炭山がいくつも見つかり、三菱や三井といった財閥が次々と炭鉱を開いた。その豊富な資源に着目した王子製紙が、現地の製紙工場を吸収合併しながら、大正から戦前にかけて樺太に9つの工場を築いた。そのうちのひとつ、恵須取工場に就職した曾祖父は、渡航から2年後、祖母を授かった。そんな曾祖父が勤めた王子の煙突は、62年間、同じ姿でずっとそこに立っていた。「ああ、戻って来たんだ」煙突を見た祖母があとで私にぽつりと言ったその一言が忘れられない。
それから4日間ほど、他の参加者と共に思い出の地を巡った。生家が建っていた場所、通った小学校、墓地、病院跡。同じ建物は残っていなかったが、川や山の位置は変わらないので、地形から判別して、当時のことを思ったに違いない。ひとつひとつ何かを確認するように、祖母の顔つきは日を追うごとに確固たるものへと変わっていった。
恵須取を去る日、バスの中から4本の煙突をじいっと祖母は見つめていた。眉頭は寄り、目尻が垂れ下がる。その目に涙はなかったが、ものすごく愛おしいものを見るように、遠ざかる街と煙突をいつまでも見つめ続けた。祖母の顔は清々しく、私はその表情にシャッターを切らずにはいられなかった。気がつくと、カメラの背面が涙で濡れていた。私の知らない祖母の表情。自分の暮らした家の跡だけではなく、さらにその先の何かに見入っていた視線。
私は見たかった。その時、祖母には見えて私に見えなかったものを。それから6回、いつか見えるのではと、その想いにすがるようにサハリンへ通い続けた。
2016年、8月も終わりに差し掛かったある日、サハリンへ電話をかけた。自分の携帯電話から、ウグレゴルスクに住むナージャという女性にだ。ダイヤルアシストで自動的に海外の電話に転送される。初めてサハリンを訪れた6年前からすると、随分簡単に連絡がとれるようになった。10回ほどの呼び出し音のあとに、「アロー?」と低い女性の声。「ナージャ?」「ダー(イエス)」「ミホコだよ」「ダー、カクジュラー?(元気か?)」元気だ、10月にサハリンに行くよ、というと「ハラショー、ハラショー(わかったよ)」とナージャ。昨年ナージャが札幌を訪れて以来1年ぶりの会話だったが、久しぶりの連絡に特段驚くわけでもなく、淡々と話し続けている。私はあまりロシア語が話せないので、知っている単語を並べ、用件を伝える。ナージャも同じく、片言の日本語を返してくれる。たった5分ほどの短い電話だったが、ウグレゴルスクへ着く日は伝わったようだ。「エストル、着く、テレフォン、ナージャかける」バス停に着いたら電話をよこせと言っている。そこにナージャがいなくても、昼間に着くバスは1本しかないので、歩いているうちにどこかで出会うだろうと、あまり心配もせず「パカパカー(またね)」と電話を終えた。2年ぶりのサハリン渡航まで1か月をきった。
記事一覧
-
2020-summer-story
02│8月12日 台湾 -
2020-summer-story
01│8月5日 東京 -
2020-summer-story
00│公開予定 -
町田恵美
01│MAX PLAN 1970-1979 -
港千尋
02│瞬間建築 -
港千尋
01│長い橋 -
関川歩
01│南方以南 the Hidden South -
呂孟恂
00│プロフィール -
町田恵美
00│プロフィール -
関川歩
00│プロフィール -
港千尋
00│プロフィール -
瀬尾夏美
05│ふるさと -
ぬかつくるとこ
05│上木戸工作室 -
辻田美穂子
05│BRIDGE STORY05 -
辻田美穂子
04│BRIDGE STORY04 -
ぬかつくるとこ
04│コイケノオイケ -
瀬尾夏美
04│架空のまち|誰かに旅をしてもらう -
ぬかつくるとこ
03│しょうへいくんのプラバン工場 -
辻田美穂子
03│BRIDGE STORY3 -
瀬尾夏美
03│なくなったまちを訪ねて -
ぬかつくるとこ
02│とだのま -
辻田美穂子
02│BRIDGE STORY02 -
02│掘る形 -
瀬尾夏美
02│山の終戦を訪ねる -
キオ・グリフィス
01│文聞録~其の一 -
辻田美穂子
01│BRIDGE STORY01 -
ぬかつくるとこ
01│「ぬか つくるとこ」とは -
瀬尾夏美
01│陸前高田にて -
01│The Color of Oil -
瀬尾夏美
00│プロフィール -
00│プロフィール -
00│プロフィール -
キオ・グリフィス
00│プロフィール -
辻田美穂子
00│プロフィール -
ぬかつくるとこ
00│プロフィール -
ムーニー・スザンヌ
05│レジリエント・アーティスト -
齋藤彰英
05│《移動すること》構造線と塩の道 ⑤ -
大谷悠
05│現代都市のアジールと「あそび」のクオリティ -
大谷悠
04│都市の「あそび」に集まるひとたち——「日本の家」となかまたち -
舩木翔平
05│新しい日常を創り出すこと -
舩木翔平
04│野菜たちの作り方 -
原亜由美
05│記憶の居場所 -
仲宗根香織
05│小舟で漕いで行く -
太田エマ
04│#IAmaMigrant -
江上賢一郎
05│『流転しつつ根をはること -マレーシア、インドネシアの芸術・文化実践- 』 -
齋藤彰英
04│《移動すること》構造線と塩の道 ④ -
ムーニー・スザンヌ
04│猫の生活:下、上、間、後ろ、向こう -
太田エマ
03│70代以上の女性:どうやって働いてきたのでしょうか? -
江上賢一郎
04│都市の瓦礫から文化をつくる。(韓国) -
仲宗根香織
04│宇宙につながる歴史、光、写真 -
原亜由美
04│リトアニアとハワイ -
大谷悠
03│「公共空間」で「あそぶ」— 小倉城を攻め落とした話 -
ムーニー・スザンヌ
03│都市発展のオルタナティブ・タイムライン -
齋藤彰英
03│《移動すること》構造線と塩の道 ③ -
舩木翔平
03│畑の中の小さなお店から始まる出来事 -
江上賢一郎
03│台南の家族たち -
仲宗根香織
03│傷の想像力 -
原亜由美
03│照らされること -
ムーニー・スザンヌ
02│包含し、守り、分ける、壁 -
齋藤彰英
02│《移動すること》構造線と塩の道 ② -
大谷悠
02│産業遺産を「アート」で「あそぶ」— ドイツの衰退工業都市に「パラダイス」をつくった話 -
舩木翔平
02│街にヤギ -
太田エマ
02│アートとプレカリアート¹ -
原亜由美
02│土地と向き合う -
江上賢一郎
02│Alternative Asia 香港編(後編) -
仲宗根香織
02│生まれ変わる街を想像する力 -
齋藤彰英
01│《移動すること》構造線と塩の道 ① -
大谷悠
01│「空き家」と「あそび」— ライプツィヒ「日本の家」 -
舩木翔平
01│ニュータウンに残された奇跡の農村風景 -
ムーニー・スザンヌ
01│場所から場所へ移動する / As We Travel from Point to Point -
原亜由美
01│夏と記憶の欠片 -
太田エマ
01│パブリックと領域
場所を持つことはパブリックを不可能にするか? -
江上賢一郎
01│Alternative Asia 香港編(前編) -
仲宗根香織
01│秘密のない風景 -
ムーニー・スザンヌ
00│プロフィール -
舩木翔平
00│プロフィール -
大谷悠
00│プロフィール -
齋藤彰英
00│プロフィール -
仲宗根香織
00│プロフィール -
原亜由美
00│プロフィール -
太田エマ
00│プロフィール -
江上賢一郎
00│プロフィール
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22