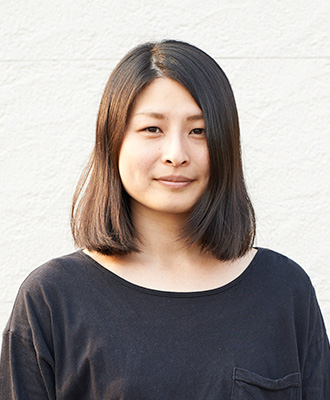
辻田美穂子
Mihoko Tsujita
故郷は文字通り、誰しもが持っている唯一無二の場所です。しかしそれは揺らぐことのない絶対的な存在なのでしょうか。16歳から19歳まで過ごしたオーストラリアでは自分が日本人であることを根本から否定されるような出来事がありました。生まれた大阪という土地で染み付いた風習を恥じ、土地柄はできるだけ隠して過ごしました。一方で、海の向こうから届く祖母からの手紙には、訪れることのできない遠い故郷の思い出が、大事に綴られていました。
他人と共有したい素晴らしい景色も、できれば隠しておきたい事柄も、写真として切り取られた「今」は、在りのままとして等価に写ります。たったひとつの場所を想い続けるということ。根を下ろさずに土地を移ろい暮らすとういうこと。2013年に北海道に移り住んで以来、これらの境界はだんだんと曖昧になりつつあります。日々の暮らしにカメラを持ち込み、全てを一旦並列にすることで、わからなさを解きほぐしていきたいと考えています。
他人と共有したい素晴らしい景色も、できれば隠しておきたい事柄も、写真として切り取られた「今」は、在りのままとして等価に写ります。たったひとつの場所を想い続けるということ。根を下ろさずに土地を移ろい暮らすとういうこと。2013年に北海道に移り住んで以来、これらの境界はだんだんと曖昧になりつつあります。日々の暮らしにカメラを持ち込み、全てを一旦並列にすることで、わからなさを解きほぐしていきたいと考えています。
01 BRIDGE STORY01
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/single-story.php on line 49

ある日夢をみた。
私の肌は白く、髪はくすんだサンディーブロンドで目は水色だった。学校には友達もたくさんいて、日常は何の問題もなく過ぎていった。しかし目覚めて朝一番に見た鏡の中には、肌が黄色く、髪も目も黒い自分がいた。オーストラリアの高校に通っていた私は、渡豪からまもなく1年が経過するというのに、学校でなかなか居場所を見つけることができずにいた。学年の約半数がアジア人、そしてそのうち三分の一が留学生という中で、私は私である前にひとりのアジア人にすぎず、私たちはまとめて”FOB”と呼ばれていた。”Fresh Off the Boat(「舟から降りて間もないもの」)”、つまりその土地へやって来てまもない移民のことだった。
どうしたら仲間として認めてもらえるのだろう、とそのことばかり考えていた。しかし短い足にスキニーパンツを合わせてみても、髪をオレンジ色にしてみても、現地人の仲間にはなれなかった。アジア人に生まれた時点で、初めから自分にそのような資格はないとまで思うようになった。私は私だと胸を張る自信もなく、故郷に対する思いもいつの間にか恥に代わり、ついにはそんな自分を自身で受け入れられなくなった。とにかく寂しくて、不安だった。
そんな時、祖母から手紙が届いた。祖母は樺太というところで生まれ、終戦後の昭和23年までそこで暮らしていた。それは北海道よりもずっと北にある島だった。戦前は中学校がなかったので、進学のために海を渡り、一時的に北海道の親戚宅に住まわせてもらっていた。時代も時代だったので、親戚は自分の子の世話でいっぱいいっぱいで、祖母は肩身の狭い思いをしたという。どれも初めて知る内容だった。そんな祖母の過去を読みながら、自分の状況が当時の祖母とどこか重なる感覚を覚えた。海を越えて知らない土地で生活をしていた祖母の不安な気持ちを、とても近くに感じた。
樺太に行こう、と最初に思ったのは写真の専門学校に入ったときだった。それまでは行ってみたいな、という気持ちはおろか、行けるのかな、という思いさえもなく、たとえそれが祖母の故郷であっても、樺太は樺太として、知識のひとつとして、ただそこに在るというだけだった。それが行ってみたいと急に、しかも強く思ったのである。写真学校の先生が「絵は自宅で座っていても描けるけれど、写真は現地に行かないと撮れない」と言った。それまでただ存在していた「樺太」と「私」の間にあった透明な脈に、血が流れ出した気がした。
祖母は23歳で大阪に嫁いでから、しばらく樺太の話を禁じられていた。古いしきたりやしがらみがまだ色濃く浸透していた大阪の農村では、北海道から嫁をもらうというのはただでさえ噂の的だったが、ましてやそれより北の「樺太」から嫁をもらうなんて、一体どこの熊ををもらうのだ、などと隣近所から噂されないためだったそうだ。しかし私が生まれて物心がついた頃には、祖母は家族の誰も知らない言葉を話すということを認識していた。英語教師の母親ですらわからない言葉が話せる祖母が、とてもかっこよく思えた。料理の手伝いをするかたわら、「じゃがいもはカルトーシカ、キャベツはカプースタ」などと教えてくれた。たくさん言葉を覚えて、母親に自慢したい。もっと教えて、と言うたびに、30年以上秘めていた思いを、次第にぽつり、ぽつりと語るようになった。
16歳で生まれた家を離れてから、私は常にエイリアンだ。国内外のあらゆる土地で暮らすということは、いつまでも外部からきた者ということで、その暮らしの中で感じるうら寂しさは心の片隅に在り続ける。しかしそれは、10年前にオーストラリアで感じた出口のない悲しみとはまた異なる。樺太に通い始めるようになり、6年がたった。自分がどこから来たのか、というルーツ探しではなく、故郷を追われてもなおひとつの土地を強く想い続ける祖母の想いに惹かれているからだ。また、その想いを辿って渡航を重ねるごとに、「故郷」と「帰属すると感じる場所」の間に存在していた自分自身のわだかまりも、少しずつ溶け出しているように思える。ただただ漂流を続け、たまたま着岸した場所に住処を持とうとしているわけではない。自分が自分を見捨てないために、足を踏み入れた土地にカメラを向けながら、このわだかまりを見つめたい。
私の肌は白く、髪はくすんだサンディーブロンドで目は水色だった。学校には友達もたくさんいて、日常は何の問題もなく過ぎていった。しかし目覚めて朝一番に見た鏡の中には、肌が黄色く、髪も目も黒い自分がいた。オーストラリアの高校に通っていた私は、渡豪からまもなく1年が経過するというのに、学校でなかなか居場所を見つけることができずにいた。学年の約半数がアジア人、そしてそのうち三分の一が留学生という中で、私は私である前にひとりのアジア人にすぎず、私たちはまとめて”FOB”と呼ばれていた。”Fresh Off the Boat(「舟から降りて間もないもの」)”、つまりその土地へやって来てまもない移民のことだった。
どうしたら仲間として認めてもらえるのだろう、とそのことばかり考えていた。しかし短い足にスキニーパンツを合わせてみても、髪をオレンジ色にしてみても、現地人の仲間にはなれなかった。アジア人に生まれた時点で、初めから自分にそのような資格はないとまで思うようになった。私は私だと胸を張る自信もなく、故郷に対する思いもいつの間にか恥に代わり、ついにはそんな自分を自身で受け入れられなくなった。とにかく寂しくて、不安だった。
そんな時、祖母から手紙が届いた。祖母は樺太というところで生まれ、終戦後の昭和23年までそこで暮らしていた。それは北海道よりもずっと北にある島だった。戦前は中学校がなかったので、進学のために海を渡り、一時的に北海道の親戚宅に住まわせてもらっていた。時代も時代だったので、親戚は自分の子の世話でいっぱいいっぱいで、祖母は肩身の狭い思いをしたという。どれも初めて知る内容だった。そんな祖母の過去を読みながら、自分の状況が当時の祖母とどこか重なる感覚を覚えた。海を越えて知らない土地で生活をしていた祖母の不安な気持ちを、とても近くに感じた。
樺太に行こう、と最初に思ったのは写真の専門学校に入ったときだった。それまでは行ってみたいな、という気持ちはおろか、行けるのかな、という思いさえもなく、たとえそれが祖母の故郷であっても、樺太は樺太として、知識のひとつとして、ただそこに在るというだけだった。それが行ってみたいと急に、しかも強く思ったのである。写真学校の先生が「絵は自宅で座っていても描けるけれど、写真は現地に行かないと撮れない」と言った。それまでただ存在していた「樺太」と「私」の間にあった透明な脈に、血が流れ出した気がした。
祖母は23歳で大阪に嫁いでから、しばらく樺太の話を禁じられていた。古いしきたりやしがらみがまだ色濃く浸透していた大阪の農村では、北海道から嫁をもらうというのはただでさえ噂の的だったが、ましてやそれより北の「樺太」から嫁をもらうなんて、一体どこの熊ををもらうのだ、などと隣近所から噂されないためだったそうだ。しかし私が生まれて物心がついた頃には、祖母は家族の誰も知らない言葉を話すということを認識していた。英語教師の母親ですらわからない言葉が話せる祖母が、とてもかっこよく思えた。料理の手伝いをするかたわら、「じゃがいもはカルトーシカ、キャベツはカプースタ」などと教えてくれた。たくさん言葉を覚えて、母親に自慢したい。もっと教えて、と言うたびに、30年以上秘めていた思いを、次第にぽつり、ぽつりと語るようになった。
16歳で生まれた家を離れてから、私は常にエイリアンだ。国内外のあらゆる土地で暮らすということは、いつまでも外部からきた者ということで、その暮らしの中で感じるうら寂しさは心の片隅に在り続ける。しかしそれは、10年前にオーストラリアで感じた出口のない悲しみとはまた異なる。樺太に通い始めるようになり、6年がたった。自分がどこから来たのか、というルーツ探しではなく、故郷を追われてもなおひとつの土地を強く想い続ける祖母の想いに惹かれているからだ。また、その想いを辿って渡航を重ねるごとに、「故郷」と「帰属すると感じる場所」の間に存在していた自分自身のわだかまりも、少しずつ溶け出しているように思える。ただただ漂流を続け、たまたま着岸した場所に住処を持とうとしているわけではない。自分が自分を見捨てないために、足を踏み入れた土地にカメラを向けながら、このわだかまりを見つめたい。
記事一覧
-
2020-summer-story
02│8月12日 台湾 -
2020-summer-story
01│8月5日 東京 -
2020-summer-story
00│公開予定 -
町田恵美
01│MAX PLAN 1970-1979 -
港千尋
02│瞬間建築 -
港千尋
01│長い橋 -
関川歩
01│南方以南 the Hidden South -
呂孟恂
00│プロフィール -
町田恵美
00│プロフィール -
関川歩
00│プロフィール -
港千尋
00│プロフィール -
瀬尾夏美
05│ふるさと -
ぬかつくるとこ
05│上木戸工作室 -
辻田美穂子
05│BRIDGE STORY05 -
辻田美穂子
04│BRIDGE STORY04 -
ぬかつくるとこ
04│コイケノオイケ -
瀬尾夏美
04│架空のまち|誰かに旅をしてもらう -
ぬかつくるとこ
03│しょうへいくんのプラバン工場 -
辻田美穂子
03│BRIDGE STORY3 -
瀬尾夏美
03│なくなったまちを訪ねて -
ぬかつくるとこ
02│とだのま -
辻田美穂子
02│BRIDGE STORY02 -
02│掘る形 -
瀬尾夏美
02│山の終戦を訪ねる -
キオ・グリフィス
01│文聞録~其の一 -
辻田美穂子
01│BRIDGE STORY01 -
ぬかつくるとこ
01│「ぬか つくるとこ」とは -
瀬尾夏美
01│陸前高田にて -
01│The Color of Oil -
瀬尾夏美
00│プロフィール -
00│プロフィール -
00│プロフィール -
キオ・グリフィス
00│プロフィール -
辻田美穂子
00│プロフィール -
ぬかつくるとこ
00│プロフィール -
ムーニー・スザンヌ
05│レジリエント・アーティスト -
齋藤彰英
05│《移動すること》構造線と塩の道 ⑤ -
大谷悠
05│現代都市のアジールと「あそび」のクオリティ -
大谷悠
04│都市の「あそび」に集まるひとたち——「日本の家」となかまたち -
舩木翔平
05│新しい日常を創り出すこと -
舩木翔平
04│野菜たちの作り方 -
原亜由美
05│記憶の居場所 -
仲宗根香織
05│小舟で漕いで行く -
太田エマ
04│#IAmaMigrant -
江上賢一郎
05│『流転しつつ根をはること -マレーシア、インドネシアの芸術・文化実践- 』 -
齋藤彰英
04│《移動すること》構造線と塩の道 ④ -
ムーニー・スザンヌ
04│猫の生活:下、上、間、後ろ、向こう -
太田エマ
03│70代以上の女性:どうやって働いてきたのでしょうか? -
江上賢一郎
04│都市の瓦礫から文化をつくる。(韓国) -
仲宗根香織
04│宇宙につながる歴史、光、写真 -
原亜由美
04│リトアニアとハワイ -
大谷悠
03│「公共空間」で「あそぶ」— 小倉城を攻め落とした話 -
ムーニー・スザンヌ
03│都市発展のオルタナティブ・タイムライン -
齋藤彰英
03│《移動すること》構造線と塩の道 ③ -
舩木翔平
03│畑の中の小さなお店から始まる出来事 -
江上賢一郎
03│台南の家族たち -
仲宗根香織
03│傷の想像力 -
原亜由美
03│照らされること -
ムーニー・スザンヌ
02│包含し、守り、分ける、壁 -
齋藤彰英
02│《移動すること》構造線と塩の道 ② -
大谷悠
02│産業遺産を「アート」で「あそぶ」— ドイツの衰退工業都市に「パラダイス」をつくった話 -
舩木翔平
02│街にヤギ -
太田エマ
02│アートとプレカリアート¹ -
原亜由美
02│土地と向き合う -
江上賢一郎
02│Alternative Asia 香港編(後編) -
仲宗根香織
02│生まれ変わる街を想像する力 -
齋藤彰英
01│《移動すること》構造線と塩の道 ① -
大谷悠
01│「空き家」と「あそび」— ライプツィヒ「日本の家」 -
舩木翔平
01│ニュータウンに残された奇跡の農村風景 -
ムーニー・スザンヌ
01│場所から場所へ移動する / As We Travel from Point to Point -
原亜由美
01│夏と記憶の欠片 -
太田エマ
01│パブリックと領域
場所を持つことはパブリックを不可能にするか? -
江上賢一郎
01│Alternative Asia 香港編(前編) -
仲宗根香織
01│秘密のない風景 -
ムーニー・スザンヌ
00│プロフィール -
舩木翔平
00│プロフィール -
大谷悠
00│プロフィール -
齋藤彰英
00│プロフィール -
仲宗根香織
00│プロフィール -
原亜由美
00│プロフィール -
太田エマ
00│プロフィール -
江上賢一郎
00│プロフィール
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22