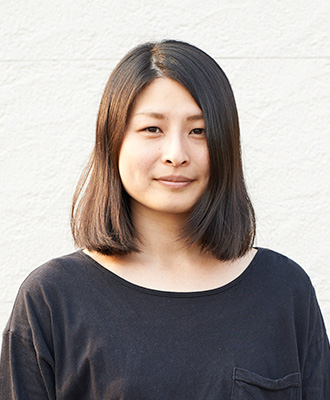
辻田美穂子
Mihoko Tsujita
故郷は文字通り、誰しもが持っている唯一無二の場所です。しかしそれは揺らぐことのない絶対的な存在なのでしょうか。16歳から19歳まで過ごしたオーストラリアでは自分が日本人であることを根本から否定されるような出来事がありました。生まれた大阪という土地で染み付いた風習を恥じ、土地柄はできるだけ隠して過ごしました。一方で、海の向こうから届く祖母からの手紙には、訪れることのできない遠い故郷の思い出が、大事に綴られていました。
他人と共有したい素晴らしい景色も、できれば隠しておきたい事柄も、写真として切り取られた「今」は、在りのままとして等価に写ります。たったひとつの場所を想い続けるということ。根を下ろさずに土地を移ろい暮らすとういうこと。2013年に北海道に移り住んで以来、これらの境界はだんだんと曖昧になりつつあります。日々の暮らしにカメラを持ち込み、全てを一旦並列にすることで、わからなさを解きほぐしていきたいと考えています。
他人と共有したい素晴らしい景色も、できれば隠しておきたい事柄も、写真として切り取られた「今」は、在りのままとして等価に写ります。たったひとつの場所を想い続けるということ。根を下ろさずに土地を移ろい暮らすとういうこと。2013年に北海道に移り住んで以来、これらの境界はだんだんと曖昧になりつつあります。日々の暮らしにカメラを持ち込み、全てを一旦並列にすることで、わからなさを解きほぐしていきたいと考えています。
04 BRIDGE STORY04
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/single-story.php on line 49

写真の学校で出会った恩師は、8×10(エイトバイテン)という大型のカメラで、様々な土地に出向いては、そこで暮らす人々を写していた。知らない人に話しかけて、写真をとらせてもらう。その行為は私が最も苦手とすることを短い時間にぎゅっと詰めこんだ作業だった。初めて出会う人に声をかける。自分がなぜカメラをもってそこに来たかを話す。写真を撮らせてとお願いする。その場限りになることもあるけれど、その接点が一点でも、一瞬でも、話しかけた瞬間から何らかの関係ができてしまう。その一連の行為は、在学中も卒業してもできないでいた。オーストラリアでの体験から、人と向き合うという行為がなかなかできなかった。
学校で最初に貸し出されるのは、28ミリの単焦点がついたフィルムカメラだ。画像を確認することもできないし、広角レンズなので、物理的にその対象物に寄らないと、画面一杯に写らない。入学した最初の年には授業の一環で、街中を歩いてスナップをした。捉えかたによっては盗撮になるような行為かもしれない。そんな怖さが頭から離れず、自分の認識の外側へいくことができないでいた。あがってきた写真には人がぽつんとフレーム内に収まっているだけで、その人がわかるような魅力などは何も写っていない。被写体に寄ることが魅力を引き出すことの全てというわけではなく、それ以前に本当に何も写っていなかったのだ。人や街は写っていても、その瞬間に決定のシャッターを切ったときの自分自身が、わからなさの恐怖のまっただ中で、混乱して、向き合っているものが見えていなかった。思い通りに写らなかったり、意図したフレーミングからずれてしまう差異が、写真にはある。しかし、そんな粋でおもしろがることのできる差異ではない。私の写真にはただただわからないが写っているばかりだった。
そんなわからないのかたまりを少しずつほどいてきたのが、サハリンへいくという行為のような気がする。もうすぐナージャと出会って7年になる。同じ場所へ通い続ける時間と関係性が比例して積み重なっていくことは、見知ったはずの「今まで通り」の中にあった発見だった。それまで、人がいなくなったり、ものが無くなってしまったり、他の人に言われたことで「今まで通り」がなくなってしまうことが、極端に苦手で怖かった。そういった問題に向き合える強さがなくて、定着できずに、わからないままその世界から剥がれてふらりと新たな地へ飛んで行ってしまう。サハリンに通い始めて3年目の夏から、ナージャは私を家に泊めてくれるようになった。その生活を写させてもらう時は、いつもどこか申し訳ない気持ちでいっぱいだった。だけど、次の年も、また次の年も、つたないロシア語でナージャに「泊まりに行ってもいい?」と電話をかけても、一度もニエット(ノー)と言われたことがない。帰る日が近づくと必ず私の腕をとり、「次はいつ来るの?」と聞いてくれる。私はずっと勘違いをしていた。キッチンの他に、二部屋しかないそのうちの一つの部屋を貸してくれること、ベッドを譲ってくれること、糖尿もちのナージャには食べられないケーキを用意して私を待っていてくれること、不自由な足で散歩についてきてくれること。そのすべてが、最大限のナージャのもてなしで、私に全力で向き合っていてくれているということだったのだ。そのことに気がついたのは、昨年の写真を見返していた時だった。
ナージャと過ごす時間は、もう異国での非日常ではなくなってきていた。朝起きて、ナージャの用意してくれたごはんを食べる。お茶を飲んで、家事をするナージャを眺めたり、手伝ったり。昼になってまた食べる。そしてお茶を飲む。ベランダに出て山を眺めたり、その辺をほっつき歩いている階下の野良犬を観察したりする。5階の部屋は日当りがとても良くて、充分に暖められたソファベッドの上でまどろんでいると、ナージャもいつの間にか横になっていて、ひまわりの種をかじりながらテレビを見ていたりする。なんでもない時間の連続の中でふとした瞬間にナージャにカメラを向ける。ナージャ、と呼びかける以外特に発する言葉もなく、写真を撮り終えるとナージャもまた、何事もなかったかのように自分の作業に戻る。まるで空気のように、その一連の行為がいつもそこに存在するかのように、ナージャは私とカメラを異質なものとして捉えない。その機会にしか行けない場所へ行ったり、常に特別なことを写したいとはあまり思わなくなったし、当初は滞在中の時間をめいっぱい使って私を外へ連れ出してくれていたナージャも、きっといつもそうしているように、ただ家で時間を過ごすようになっていた。カメラを持ち込むというのは、撮る側も撮られる側にも異質な行為であるけれど、それを呼吸のような自発的行為として両者で共有できたとき、その人との関係性が生まれるのかもしれないと今は思う。
ナージャの家にはいつも季節ごとに採れたものがある。春にはししゃもや行者ニンニク、夏にはこんぶや、ベリーのジャム、秋にはキノコの酢漬け。保存の利くものはたくさん瓶詰めにして親戚に配り、あとは冬の間、山の雪が無くなるまで、海の氷がとけだすまで、少しずつ大事に食べる。街を歩けば、誰かに声をかけない日はない。「ナージャ、元気かい?」みんなそう聞く。季節の移ろいの中にその暮らしはただありありと存在している。私がずっと避けてきた、蓄積された日々は、とてもまぶしく見えるようになった。
学校で最初に貸し出されるのは、28ミリの単焦点がついたフィルムカメラだ。画像を確認することもできないし、広角レンズなので、物理的にその対象物に寄らないと、画面一杯に写らない。入学した最初の年には授業の一環で、街中を歩いてスナップをした。捉えかたによっては盗撮になるような行為かもしれない。そんな怖さが頭から離れず、自分の認識の外側へいくことができないでいた。あがってきた写真には人がぽつんとフレーム内に収まっているだけで、その人がわかるような魅力などは何も写っていない。被写体に寄ることが魅力を引き出すことの全てというわけではなく、それ以前に本当に何も写っていなかったのだ。人や街は写っていても、その瞬間に決定のシャッターを切ったときの自分自身が、わからなさの恐怖のまっただ中で、混乱して、向き合っているものが見えていなかった。思い通りに写らなかったり、意図したフレーミングからずれてしまう差異が、写真にはある。しかし、そんな粋でおもしろがることのできる差異ではない。私の写真にはただただわからないが写っているばかりだった。
そんなわからないのかたまりを少しずつほどいてきたのが、サハリンへいくという行為のような気がする。もうすぐナージャと出会って7年になる。同じ場所へ通い続ける時間と関係性が比例して積み重なっていくことは、見知ったはずの「今まで通り」の中にあった発見だった。それまで、人がいなくなったり、ものが無くなってしまったり、他の人に言われたことで「今まで通り」がなくなってしまうことが、極端に苦手で怖かった。そういった問題に向き合える強さがなくて、定着できずに、わからないままその世界から剥がれてふらりと新たな地へ飛んで行ってしまう。サハリンに通い始めて3年目の夏から、ナージャは私を家に泊めてくれるようになった。その生活を写させてもらう時は、いつもどこか申し訳ない気持ちでいっぱいだった。だけど、次の年も、また次の年も、つたないロシア語でナージャに「泊まりに行ってもいい?」と電話をかけても、一度もニエット(ノー)と言われたことがない。帰る日が近づくと必ず私の腕をとり、「次はいつ来るの?」と聞いてくれる。私はずっと勘違いをしていた。キッチンの他に、二部屋しかないそのうちの一つの部屋を貸してくれること、ベッドを譲ってくれること、糖尿もちのナージャには食べられないケーキを用意して私を待っていてくれること、不自由な足で散歩についてきてくれること。そのすべてが、最大限のナージャのもてなしで、私に全力で向き合っていてくれているということだったのだ。そのことに気がついたのは、昨年の写真を見返していた時だった。
ナージャと過ごす時間は、もう異国での非日常ではなくなってきていた。朝起きて、ナージャの用意してくれたごはんを食べる。お茶を飲んで、家事をするナージャを眺めたり、手伝ったり。昼になってまた食べる。そしてお茶を飲む。ベランダに出て山を眺めたり、その辺をほっつき歩いている階下の野良犬を観察したりする。5階の部屋は日当りがとても良くて、充分に暖められたソファベッドの上でまどろんでいると、ナージャもいつの間にか横になっていて、ひまわりの種をかじりながらテレビを見ていたりする。なんでもない時間の連続の中でふとした瞬間にナージャにカメラを向ける。ナージャ、と呼びかける以外特に発する言葉もなく、写真を撮り終えるとナージャもまた、何事もなかったかのように自分の作業に戻る。まるで空気のように、その一連の行為がいつもそこに存在するかのように、ナージャは私とカメラを異質なものとして捉えない。その機会にしか行けない場所へ行ったり、常に特別なことを写したいとはあまり思わなくなったし、当初は滞在中の時間をめいっぱい使って私を外へ連れ出してくれていたナージャも、きっといつもそうしているように、ただ家で時間を過ごすようになっていた。カメラを持ち込むというのは、撮る側も撮られる側にも異質な行為であるけれど、それを呼吸のような自発的行為として両者で共有できたとき、その人との関係性が生まれるのかもしれないと今は思う。
ナージャの家にはいつも季節ごとに採れたものがある。春にはししゃもや行者ニンニク、夏にはこんぶや、ベリーのジャム、秋にはキノコの酢漬け。保存の利くものはたくさん瓶詰めにして親戚に配り、あとは冬の間、山の雪が無くなるまで、海の氷がとけだすまで、少しずつ大事に食べる。街を歩けば、誰かに声をかけない日はない。「ナージャ、元気かい?」みんなそう聞く。季節の移ろいの中にその暮らしはただありありと存在している。私がずっと避けてきた、蓄積された日々は、とてもまぶしく見えるようになった。
記事一覧
-
2020-summer-story
02│8月12日 台湾 -
2020-summer-story
01│8月5日 東京 -
2020-summer-story
00│公開予定 -
町田恵美
01│MAX PLAN 1970-1979 -
港千尋
02│瞬間建築 -
港千尋
01│長い橋 -
関川歩
01│南方以南 the Hidden South -
呂孟恂
00│プロフィール -
町田恵美
00│プロフィール -
関川歩
00│プロフィール -
港千尋
00│プロフィール -
瀬尾夏美
05│ふるさと -
ぬかつくるとこ
05│上木戸工作室 -
辻田美穂子
05│BRIDGE STORY05 -
辻田美穂子
04│BRIDGE STORY04 -
ぬかつくるとこ
04│コイケノオイケ -
瀬尾夏美
04│架空のまち|誰かに旅をしてもらう -
ぬかつくるとこ
03│しょうへいくんのプラバン工場 -
辻田美穂子
03│BRIDGE STORY3 -
瀬尾夏美
03│なくなったまちを訪ねて -
ぬかつくるとこ
02│とだのま -
辻田美穂子
02│BRIDGE STORY02 -
02│掘る形 -
瀬尾夏美
02│山の終戦を訪ねる -
キオ・グリフィス
01│文聞録~其の一 -
辻田美穂子
01│BRIDGE STORY01 -
ぬかつくるとこ
01│「ぬか つくるとこ」とは -
瀬尾夏美
01│陸前高田にて -
01│The Color of Oil -
瀬尾夏美
00│プロフィール -
00│プロフィール -
00│プロフィール -
キオ・グリフィス
00│プロフィール -
辻田美穂子
00│プロフィール -
ぬかつくるとこ
00│プロフィール -
ムーニー・スザンヌ
05│レジリエント・アーティスト -
齋藤彰英
05│《移動すること》構造線と塩の道 ⑤ -
大谷悠
05│現代都市のアジールと「あそび」のクオリティ -
大谷悠
04│都市の「あそび」に集まるひとたち——「日本の家」となかまたち -
舩木翔平
05│新しい日常を創り出すこと -
舩木翔平
04│野菜たちの作り方 -
原亜由美
05│記憶の居場所 -
仲宗根香織
05│小舟で漕いで行く -
太田エマ
04│#IAmaMigrant -
江上賢一郎
05│『流転しつつ根をはること -マレーシア、インドネシアの芸術・文化実践- 』 -
齋藤彰英
04│《移動すること》構造線と塩の道 ④ -
ムーニー・スザンヌ
04│猫の生活:下、上、間、後ろ、向こう -
太田エマ
03│70代以上の女性:どうやって働いてきたのでしょうか? -
江上賢一郎
04│都市の瓦礫から文化をつくる。(韓国) -
仲宗根香織
04│宇宙につながる歴史、光、写真 -
原亜由美
04│リトアニアとハワイ -
大谷悠
03│「公共空間」で「あそぶ」— 小倉城を攻め落とした話 -
ムーニー・スザンヌ
03│都市発展のオルタナティブ・タイムライン -
齋藤彰英
03│《移動すること》構造線と塩の道 ③ -
舩木翔平
03│畑の中の小さなお店から始まる出来事 -
江上賢一郎
03│台南の家族たち -
仲宗根香織
03│傷の想像力 -
原亜由美
03│照らされること -
ムーニー・スザンヌ
02│包含し、守り、分ける、壁 -
齋藤彰英
02│《移動すること》構造線と塩の道 ② -
大谷悠
02│産業遺産を「アート」で「あそぶ」— ドイツの衰退工業都市に「パラダイス」をつくった話 -
舩木翔平
02│街にヤギ -
太田エマ
02│アートとプレカリアート¹ -
原亜由美
02│土地と向き合う -
江上賢一郎
02│Alternative Asia 香港編(後編) -
仲宗根香織
02│生まれ変わる街を想像する力 -
齋藤彰英
01│《移動すること》構造線と塩の道 ① -
大谷悠
01│「空き家」と「あそび」— ライプツィヒ「日本の家」 -
舩木翔平
01│ニュータウンに残された奇跡の農村風景 -
ムーニー・スザンヌ
01│場所から場所へ移動する / As We Travel from Point to Point -
原亜由美
01│夏と記憶の欠片 -
太田エマ
01│パブリックと領域
場所を持つことはパブリックを不可能にするか? -
江上賢一郎
01│Alternative Asia 香港編(前編) -
仲宗根香織
01│秘密のない風景 -
ムーニー・スザンヌ
00│プロフィール -
舩木翔平
00│プロフィール -
大谷悠
00│プロフィール -
齋藤彰英
00│プロフィール -
仲宗根香織
00│プロフィール -
原亜由美
00│プロフィール -
太田エマ
00│プロフィール -
江上賢一郎
00│プロフィール
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22