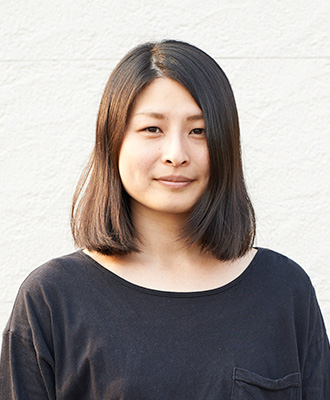
辻田美穂子
Mihoko Tsujita
故郷は文字通り、誰しもが持っている唯一無二の場所です。しかしそれは揺らぐことのない絶対的な存在なのでしょうか。16歳から19歳まで過ごしたオーストラリアでは自分が日本人であることを根本から否定されるような出来事がありました。生まれた大阪という土地で染み付いた風習を恥じ、土地柄はできるだけ隠して過ごしました。一方で、海の向こうから届く祖母からの手紙には、訪れることのできない遠い故郷の思い出が、大事に綴られていました。
他人と共有したい素晴らしい景色も、できれば隠しておきたい事柄も、写真として切り取られた「今」は、在りのままとして等価に写ります。たったひとつの場所を想い続けるということ。根を下ろさずに土地を移ろい暮らすとういうこと。2013年に北海道に移り住んで以来、これらの境界はだんだんと曖昧になりつつあります。日々の暮らしにカメラを持ち込み、全てを一旦並列にすることで、わからなさを解きほぐしていきたいと考えています。
他人と共有したい素晴らしい景色も、できれば隠しておきたい事柄も、写真として切り取られた「今」は、在りのままとして等価に写ります。たったひとつの場所を想い続けるということ。根を下ろさずに土地を移ろい暮らすとういうこと。2013年に北海道に移り住んで以来、これらの境界はだんだんと曖昧になりつつあります。日々の暮らしにカメラを持ち込み、全てを一旦並列にすることで、わからなさを解きほぐしていきたいと考えています。
03 BRIDGE STORY3
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/single-story.php on line 49

約半年もの間、雪に閉じ込められる北国の、湿気を十二分に溜め込んだ澱のような空気。長い間しまわれていた箱を開ける時のようなカビ臭さ。船が着くホルムスクの港も、飛行機で降り立つユジノサハリンスクの空港も、ホテルも駅もアパートも、一歩建物へ入ると、そのにおいがある。私にとってそれは、第一に感じられるサハリンだった。撮影を始めた頃は重く淀んだその空気が苦手であった。常に新しいものが作られ、時代にそぐわないものは壊され、そしてまた更地になるような、自分の暮らしていた大阪や東京では嗅ぐことのないにおい。2年半ぶりのサハリン渡航で、真っ先に思い出したのがそのにおいだった。記憶と嗅覚は直結していると聞いたことがある。もはや建物の中のにおいだけではない。バスで何時間も走る土埃舞う悪路、散歩するウグレゴルスクの並木道など、私の記憶の中のサハリンは、建物の外でさえも全てがそのにおいに包まれているような気さえした。サハリンへ降り立った瞬間、その空気を肺いっぱいに吸い込みたい。そんな密かな楽しみと共に、飛行機に乗り込んだ。
午後2時30分、バスはウグレゴルスクへ到着した。バスを降りると、ターミナルには家族の帰りを待つ街の住人がたくさんいた。その群衆の中に、ナージャの夫のスラバが立っている。ナージャに最後に連絡をしたのはこの街へ到着する4日前。「6日にバスに乗るから」とだけ告げた。州都のユジノサハリンスクからウグレゴルスクの街に着くバスは朝と夕方の1日2便。信号があるのは街の中心部を抜けるまでのほんの数キロの間なので、バスがひどく故障しない限り、毎日ほぼ同じ時刻に到着するのだ。
2年半ぶりに会うスラバは、いつものように表情を変えることなく、黒い革ジャケットのポケットに両手を突っ込みじっと立っている。北海道よりも数百キロ北へ位置するその街の寒さは、10月の頭とは言え、もう氷点下に近いのではないだろうか。私が「スラバ!」と手を挙げると、ごつごつとした右手を力強く差し出した。
バスターミナルから2、3分も歩けば、ナージャ一家が住むアパートがある。入り口の重い鉄扉を開けると、ちょうど西日が踊り場を照らしていて、建物の中はすこし暖かい。5階まで一気に階段を登ると、バックパックと背中の間に汗がにじみ出るのがわかった。49と書かれた部屋の呼び鈴を勢いよく押すと、電子化された「エリーゼのために」が軽快に鳴る。ナージャの足音が近づき、「ミホー」と笑顔でドアを開けてくれた。家に入るなり、「クーシェチ(食べなさい)」と言ってキッチンに私を連れて行き、大きなホーロー鍋にたっぷりと用意したボルシチを、スープ皿に注いでくれた。加賀谷ナージャは、樺太がソ連領になってからもこの地にとどまった日本人家族のひとりで、6年前に墓参団と共に初めてこの街に訪れた時に出会った。4年前から、ウグレゴルスクに滞在する際にはナージャの家に泊めてもらっている。今回の滞在中、ナージャは私と入れ違いでユジノサハリンスクへ泊まりがけで行く用事があったので、不在の数日間はスラバが相手をしてくれた。
ナージャが出かけた初日、スラバは友達に頼んで車を借り、海の方へ連れて行ってくれた。海沿いに点在する日本時代の遺構を訪れたり、浜辺をぶらぶらしたりしながら、特にこれといった目的のない2時間ほどのドライブ。その後、街の中心部で友人と別れ、スラバは買い物があるというので、一旦別行動をとることになった。思えばたった一人で街を歩くというのは、今まであまりなかった。ナージャがあっちへこっちへと私を連れ出していたからだ。街を東西に走る大通りには、いつの時代から使われているのかわからない郵便局の車がひっきりなしに走っていて、通りに面した小さな広場にはいつものように鳩の大群が、バーブシカのおこぼれを待ちながら日だまりでめいめいの時間を過ごしている。その時間は写真を撮るという目的を忘れて、まるでそれが日常かのように、ただ歩くのがとても気持ちがよかった。午後に差し掛かった斜陽は、もう数日もないであろう褪色した紅葉の間から、漏れてきらめいている。その下の歩道を、目的のある人は確かな、軽快な足取りで、そうでない人たちは晩秋の陽光を慈しむように、ゆっくりと歩いている。その景色はとても美しかった。ふと道路の反対側に目をやると、スラバがゆっくりと追いついてくるところだった。こちら側へ渡って来たので、今度は二人でゆっくりと歩いた。スラバが公園のベンチに腰掛けた。3年前に事故で痛めた膝の調子がよくないと言って、すこし休憩をした。革ジャケットの内ポケットから、ウォッカの小瓶を取り出した。先ほどの買い物とはこれだったようだ。「ナージャに言うなよ」と言って、やっとの思いでオアシスに辿り着いた砂漠の旅人のごとく、瓶の半分ほどごくごくと流し込んだ。それから、おう、と思い出したように、私にチョコレートバーをくれた。少し要るかと尋ねたら、全部お前が食べなさいと言った。そのまま二人で、目の前の土管工事の様子をながめた。黒い犬が近づいて来た。その犬は、食べ物を欲しがるわけでもなく、私たちがそこに座っているから来たのでもなく、あたりを一心不乱に嗅ぎ回っている。彼もまた、いつものように日常を送っているだけのようであった。
公園を離れて再び歩き出すと、以前立ち寄ったことのあるスラバの友人のアパートの下を通りがかった。サーシャは元気かと尋ねると、「心臓発作で死んだ」、と思いがけない応えが返ってきた。昼間からスラバと二人でウォッカをあおり、気を良くし古い写真を引っ張りだして、自分の娘の話を聞かせてくれたサーシャ。4階のアパートを見上げると、人の気配が消えた空っぽの窓が目に入った。
スラバは、「ターニャのマガジン(売店)に寄ろう」と言った。ターニャとは誰だったか。記憶をたどったが、なかなかピンとこない。店に入ると、中には従業員の女性が二人いた。ターニャはいるか、と聞くと、一人がバックヤードへ消えた。すぐに朝鮮系の男性が表に出てきて、あっと思った。ターニャは、ナージャの“ムスメ”時代からの友人で、4年前に写真を撮らせてもらったが、私はそれっきり会っていなかった。彼はターニャの夫だった。「こっちに来い」というスラバを追って、裏口からバックヤードへと入った。ターニャの夫が、「ミホコ」と言ったので、私の名前を覚えていたことに驚いた。間もなく、ターニャが現れた。やはり、「ミホコ!」と開口一番に言った。小さい女の子を抱いていた。どうやら孫娘のようだ。ミラーナというその女の子は2歳になったと言っていた。私の名を呼びながら、ロシア人の青年がどこからともなく現れた。彼のことは思い出せなかったが、青年は私の顔を見て終始ニコニコしていた。奥から更に見覚えのある女性が出て来た。ターニャの娘、ミラーナの母親だ。彼女も私の顔を見るなり、元気か、と尋ねた。今も札幌にいるのか、結婚はしたのか、仕事はどうだ。バックヤードはとても賑やかになった。帰る時、ターニャは手土産にと、店の陳列棚からブルーベリーのマフィンをとり、持たせてくれた。
翌日、スラバは友達の家に行くと出かけてしまったので、一人で街に出た。ふと思い立って、以前歩いた川沿いの道をぶらぶらと歩いていると、木柵のむこうから獰猛な犬に吠えられた。咆哮を制止する男性の声がしたので、思い切って「ズドラーストヴィーチェ(こんにちは)」、と呼びかけると、見たことのある立派な白い眉毛の年配の男性が扉を開けてくれた。なぜか、まず自分が不審者ではないことを伝えようと、「以前、畑、おばさん」と知っている単語を必死に思い出しながら口にすると、「ずっと前に、チリムシャをあげたよな」と男性は言った。2年前の春、すぐ側のダーチャでチリムシャ(行者ニンニク)を分けてくれた女性の夫だった。中を見てもいいか、と聞くと、どうぞ、とダーチャに招き入れてくれた。ダーチャとは、自宅とは別にある家庭菜園付き別荘のような場所だが、この辺りは別荘という響きから想像しうる華美なものではなく、あくまで畑仕事をする傍ら休む小屋という感じのものが多い。おじさんのダーチャはとても丁寧に手入れされていて、コンパクトな敷地内にはきちんと区画整理がなされた畑用スペースや、ドラム缶でできたペチカ(火をおこすところ)、小さくかわいらしい花壇などがあった。獰猛な犬は、スキさえあれば噛み付いてやろうとばかりに私を睨んでいたが、家主に大声で一喝されると、素直に自分の小屋へ戻って行った。ダーチャを奥へ進みながら、畑を指差し、ここにはなにが植えてあるの、と片言のロシア語で尋ねると、説明してくれたが、聞き取れたのはカルトーシカ(じゃがいも)とマルコーフカ(にんじん)だけだった。それでもうなずいていると、おじさんは身振り手振りひたすらしゃべり続けた。
その翌日、何の気なしにベランダに出てみると、ダーチャのおじさんがアパートの下を歩いているのが見えた。「ジャージャ!(おじさん)」と呼びかけると、「プリヴィエート!(やあ)」と手を挙げてくれた。
午後2時を過ぎた頃、スラバが「ナージャ、ナージャ」と言って部屋に入ってきた。今日はナージャがユジノサハリンスクから戻ってくる日だ。5階のベランダからは、バスターミナルが見える。どうやらバスはまだ到着していないようだ。5分ほどしてスラバは再びベランダに出た。私にちらりと目配せをしたので、ベランダへ出ると、真っ赤なジャケットを着たナージャがこちらへ向かって歩いているところだった。しばらくして「エリーゼのために」が家中に鳴り響いた。相変わらず笑顔のナージャが、「ミホコーゲンキー?」と尋ねた。キッチンに入ってきたスラバをちらりと見て「ノンベエ、サケ、だ?」と言った。ナージャは冗談半分に、時々酒好きの夫を、ノンベエ、と呼ぶ。留守中にスラバが酒を浴びるほど呑んでいたのはすでにお見通しなようで、その答えに一瞬ひるんだが、約束を思い出して「呑んでなかったよ」と言うと、ナージャは大声で笑い出した。
この街へ来るのは、これで7度目になる。懐かしさにひたる心地よさよりも、私を温かい気持ちにさせたのは、この街の住人との再会だ。ナージャやスラバはもちろんのこと、マガジンのターニャ、その家族や従業員。行者ニンニクをくれたダーチャのおじさん。他にも、毎回街でばったり会う日本語を話す朝鮮人のおばあさん、クリルへ行こうと以前誘ってくれたラリッサ。バスの運転手としてこの街で暮らすスラバの弟、オレグ。たった数日の滞在で、偶然にも自分の知っているほとんどの人たちに出会えたのだ。
初めてこの街へ来た時、自分が何者で、ここへ何をしにきたかということを説明しなければならないと思っていた。そう説明する間もないすれ違う人々の視線はとても気になったし、一人で街を歩いていると、「日本人か、朝鮮人か」と急に声をかけられることもあった。極東の田舎、陸の孤島とさえ呼ばれるこの街に、日本からの墓参以外で訪れる外国人など滅多にいないからだろう。いつも何かを気にしながら歩くサハリンは、窮屈で辛かった。しかし、あの人、あの人と、その面々を目に浮かばせながら街を歩いていると、その漠然とした不安な気持ちがなくなっていくようだった。属しているか否かを決めるのは、その土地の住人でもあり、自分自身でもあり、そして、そのどちらでもない。土地や国や人種といった大きな枠に自分を閉じ込めていたのは、自分自身なのだと思う。容易にぬぐい去れない過去を受け入れたり、勝手の違いに理解を示したりするのではなく、目の前の事象にただ抗わずに向かい合うことができたとき、初めてその場所が心地よいと思えるのかもしれない。そしてそう思わせてくれる最も大きなきっかけは、そこに暮らす人だ。
この街には、私の名を呼び、笑ってくれる人がいる。だからまた来たいと思う。私にとってのサハリンは、祖母から聞いていた「異国になった遠い街」ではなくなっていくような気がした。
2年半ぶりのサハリンは、ずっと心地がよかった。この時間が終わってほしくないとも思った。今回の滞在中、以前はどこにでもあったあのサハリンのにおいはかぐことができなかったが、もしかするといつの間にかその空気を吸っていたのかもしれない。それはもう、淀んだ重い異質なものではなく、そのフィルターが取れたサハリンとして体の中に取り込まれ、血液に乗り全身に巡っていたのかもしれない。そんなことを考えていると、新千歳空港の到着ロビーのドアが開いた瞬間、はっとする空気があった。管理された空調の生温さ。隅々まで掃除の行き届いた場所からは本来するはずのないにおい。しかしそれもすぐに気にならなくなった。
午後2時30分、バスはウグレゴルスクへ到着した。バスを降りると、ターミナルには家族の帰りを待つ街の住人がたくさんいた。その群衆の中に、ナージャの夫のスラバが立っている。ナージャに最後に連絡をしたのはこの街へ到着する4日前。「6日にバスに乗るから」とだけ告げた。州都のユジノサハリンスクからウグレゴルスクの街に着くバスは朝と夕方の1日2便。信号があるのは街の中心部を抜けるまでのほんの数キロの間なので、バスがひどく故障しない限り、毎日ほぼ同じ時刻に到着するのだ。
2年半ぶりに会うスラバは、いつものように表情を変えることなく、黒い革ジャケットのポケットに両手を突っ込みじっと立っている。北海道よりも数百キロ北へ位置するその街の寒さは、10月の頭とは言え、もう氷点下に近いのではないだろうか。私が「スラバ!」と手を挙げると、ごつごつとした右手を力強く差し出した。
バスターミナルから2、3分も歩けば、ナージャ一家が住むアパートがある。入り口の重い鉄扉を開けると、ちょうど西日が踊り場を照らしていて、建物の中はすこし暖かい。5階まで一気に階段を登ると、バックパックと背中の間に汗がにじみ出るのがわかった。49と書かれた部屋の呼び鈴を勢いよく押すと、電子化された「エリーゼのために」が軽快に鳴る。ナージャの足音が近づき、「ミホー」と笑顔でドアを開けてくれた。家に入るなり、「クーシェチ(食べなさい)」と言ってキッチンに私を連れて行き、大きなホーロー鍋にたっぷりと用意したボルシチを、スープ皿に注いでくれた。加賀谷ナージャは、樺太がソ連領になってからもこの地にとどまった日本人家族のひとりで、6年前に墓参団と共に初めてこの街に訪れた時に出会った。4年前から、ウグレゴルスクに滞在する際にはナージャの家に泊めてもらっている。今回の滞在中、ナージャは私と入れ違いでユジノサハリンスクへ泊まりがけで行く用事があったので、不在の数日間はスラバが相手をしてくれた。
ナージャが出かけた初日、スラバは友達に頼んで車を借り、海の方へ連れて行ってくれた。海沿いに点在する日本時代の遺構を訪れたり、浜辺をぶらぶらしたりしながら、特にこれといった目的のない2時間ほどのドライブ。その後、街の中心部で友人と別れ、スラバは買い物があるというので、一旦別行動をとることになった。思えばたった一人で街を歩くというのは、今まであまりなかった。ナージャがあっちへこっちへと私を連れ出していたからだ。街を東西に走る大通りには、いつの時代から使われているのかわからない郵便局の車がひっきりなしに走っていて、通りに面した小さな広場にはいつものように鳩の大群が、バーブシカのおこぼれを待ちながら日だまりでめいめいの時間を過ごしている。その時間は写真を撮るという目的を忘れて、まるでそれが日常かのように、ただ歩くのがとても気持ちがよかった。午後に差し掛かった斜陽は、もう数日もないであろう褪色した紅葉の間から、漏れてきらめいている。その下の歩道を、目的のある人は確かな、軽快な足取りで、そうでない人たちは晩秋の陽光を慈しむように、ゆっくりと歩いている。その景色はとても美しかった。ふと道路の反対側に目をやると、スラバがゆっくりと追いついてくるところだった。こちら側へ渡って来たので、今度は二人でゆっくりと歩いた。スラバが公園のベンチに腰掛けた。3年前に事故で痛めた膝の調子がよくないと言って、すこし休憩をした。革ジャケットの内ポケットから、ウォッカの小瓶を取り出した。先ほどの買い物とはこれだったようだ。「ナージャに言うなよ」と言って、やっとの思いでオアシスに辿り着いた砂漠の旅人のごとく、瓶の半分ほどごくごくと流し込んだ。それから、おう、と思い出したように、私にチョコレートバーをくれた。少し要るかと尋ねたら、全部お前が食べなさいと言った。そのまま二人で、目の前の土管工事の様子をながめた。黒い犬が近づいて来た。その犬は、食べ物を欲しがるわけでもなく、私たちがそこに座っているから来たのでもなく、あたりを一心不乱に嗅ぎ回っている。彼もまた、いつものように日常を送っているだけのようであった。
公園を離れて再び歩き出すと、以前立ち寄ったことのあるスラバの友人のアパートの下を通りがかった。サーシャは元気かと尋ねると、「心臓発作で死んだ」、と思いがけない応えが返ってきた。昼間からスラバと二人でウォッカをあおり、気を良くし古い写真を引っ張りだして、自分の娘の話を聞かせてくれたサーシャ。4階のアパートを見上げると、人の気配が消えた空っぽの窓が目に入った。
スラバは、「ターニャのマガジン(売店)に寄ろう」と言った。ターニャとは誰だったか。記憶をたどったが、なかなかピンとこない。店に入ると、中には従業員の女性が二人いた。ターニャはいるか、と聞くと、一人がバックヤードへ消えた。すぐに朝鮮系の男性が表に出てきて、あっと思った。ターニャは、ナージャの“ムスメ”時代からの友人で、4年前に写真を撮らせてもらったが、私はそれっきり会っていなかった。彼はターニャの夫だった。「こっちに来い」というスラバを追って、裏口からバックヤードへと入った。ターニャの夫が、「ミホコ」と言ったので、私の名前を覚えていたことに驚いた。間もなく、ターニャが現れた。やはり、「ミホコ!」と開口一番に言った。小さい女の子を抱いていた。どうやら孫娘のようだ。ミラーナというその女の子は2歳になったと言っていた。私の名を呼びながら、ロシア人の青年がどこからともなく現れた。彼のことは思い出せなかったが、青年は私の顔を見て終始ニコニコしていた。奥から更に見覚えのある女性が出て来た。ターニャの娘、ミラーナの母親だ。彼女も私の顔を見るなり、元気か、と尋ねた。今も札幌にいるのか、結婚はしたのか、仕事はどうだ。バックヤードはとても賑やかになった。帰る時、ターニャは手土産にと、店の陳列棚からブルーベリーのマフィンをとり、持たせてくれた。
翌日、スラバは友達の家に行くと出かけてしまったので、一人で街に出た。ふと思い立って、以前歩いた川沿いの道をぶらぶらと歩いていると、木柵のむこうから獰猛な犬に吠えられた。咆哮を制止する男性の声がしたので、思い切って「ズドラーストヴィーチェ(こんにちは)」、と呼びかけると、見たことのある立派な白い眉毛の年配の男性が扉を開けてくれた。なぜか、まず自分が不審者ではないことを伝えようと、「以前、畑、おばさん」と知っている単語を必死に思い出しながら口にすると、「ずっと前に、チリムシャをあげたよな」と男性は言った。2年前の春、すぐ側のダーチャでチリムシャ(行者ニンニク)を分けてくれた女性の夫だった。中を見てもいいか、と聞くと、どうぞ、とダーチャに招き入れてくれた。ダーチャとは、自宅とは別にある家庭菜園付き別荘のような場所だが、この辺りは別荘という響きから想像しうる華美なものではなく、あくまで畑仕事をする傍ら休む小屋という感じのものが多い。おじさんのダーチャはとても丁寧に手入れされていて、コンパクトな敷地内にはきちんと区画整理がなされた畑用スペースや、ドラム缶でできたペチカ(火をおこすところ)、小さくかわいらしい花壇などがあった。獰猛な犬は、スキさえあれば噛み付いてやろうとばかりに私を睨んでいたが、家主に大声で一喝されると、素直に自分の小屋へ戻って行った。ダーチャを奥へ進みながら、畑を指差し、ここにはなにが植えてあるの、と片言のロシア語で尋ねると、説明してくれたが、聞き取れたのはカルトーシカ(じゃがいも)とマルコーフカ(にんじん)だけだった。それでもうなずいていると、おじさんは身振り手振りひたすらしゃべり続けた。
その翌日、何の気なしにベランダに出てみると、ダーチャのおじさんがアパートの下を歩いているのが見えた。「ジャージャ!(おじさん)」と呼びかけると、「プリヴィエート!(やあ)」と手を挙げてくれた。
午後2時を過ぎた頃、スラバが「ナージャ、ナージャ」と言って部屋に入ってきた。今日はナージャがユジノサハリンスクから戻ってくる日だ。5階のベランダからは、バスターミナルが見える。どうやらバスはまだ到着していないようだ。5分ほどしてスラバは再びベランダに出た。私にちらりと目配せをしたので、ベランダへ出ると、真っ赤なジャケットを着たナージャがこちらへ向かって歩いているところだった。しばらくして「エリーゼのために」が家中に鳴り響いた。相変わらず笑顔のナージャが、「ミホコーゲンキー?」と尋ねた。キッチンに入ってきたスラバをちらりと見て「ノンベエ、サケ、だ?」と言った。ナージャは冗談半分に、時々酒好きの夫を、ノンベエ、と呼ぶ。留守中にスラバが酒を浴びるほど呑んでいたのはすでにお見通しなようで、その答えに一瞬ひるんだが、約束を思い出して「呑んでなかったよ」と言うと、ナージャは大声で笑い出した。
この街へ来るのは、これで7度目になる。懐かしさにひたる心地よさよりも、私を温かい気持ちにさせたのは、この街の住人との再会だ。ナージャやスラバはもちろんのこと、マガジンのターニャ、その家族や従業員。行者ニンニクをくれたダーチャのおじさん。他にも、毎回街でばったり会う日本語を話す朝鮮人のおばあさん、クリルへ行こうと以前誘ってくれたラリッサ。バスの運転手としてこの街で暮らすスラバの弟、オレグ。たった数日の滞在で、偶然にも自分の知っているほとんどの人たちに出会えたのだ。
初めてこの街へ来た時、自分が何者で、ここへ何をしにきたかということを説明しなければならないと思っていた。そう説明する間もないすれ違う人々の視線はとても気になったし、一人で街を歩いていると、「日本人か、朝鮮人か」と急に声をかけられることもあった。極東の田舎、陸の孤島とさえ呼ばれるこの街に、日本からの墓参以外で訪れる外国人など滅多にいないからだろう。いつも何かを気にしながら歩くサハリンは、窮屈で辛かった。しかし、あの人、あの人と、その面々を目に浮かばせながら街を歩いていると、その漠然とした不安な気持ちがなくなっていくようだった。属しているか否かを決めるのは、その土地の住人でもあり、自分自身でもあり、そして、そのどちらでもない。土地や国や人種といった大きな枠に自分を閉じ込めていたのは、自分自身なのだと思う。容易にぬぐい去れない過去を受け入れたり、勝手の違いに理解を示したりするのではなく、目の前の事象にただ抗わずに向かい合うことができたとき、初めてその場所が心地よいと思えるのかもしれない。そしてそう思わせてくれる最も大きなきっかけは、そこに暮らす人だ。
この街には、私の名を呼び、笑ってくれる人がいる。だからまた来たいと思う。私にとってのサハリンは、祖母から聞いていた「異国になった遠い街」ではなくなっていくような気がした。
2年半ぶりのサハリンは、ずっと心地がよかった。この時間が終わってほしくないとも思った。今回の滞在中、以前はどこにでもあったあのサハリンのにおいはかぐことができなかったが、もしかするといつの間にかその空気を吸っていたのかもしれない。それはもう、淀んだ重い異質なものではなく、そのフィルターが取れたサハリンとして体の中に取り込まれ、血液に乗り全身に巡っていたのかもしれない。そんなことを考えていると、新千歳空港の到着ロビーのドアが開いた瞬間、はっとする空気があった。管理された空調の生温さ。隅々まで掃除の行き届いた場所からは本来するはずのないにおい。しかしそれもすぐに気にならなくなった。
記事一覧
-
2020-summer-story
02│8月12日 台湾 -
2020-summer-story
01│8月5日 東京 -
2020-summer-story
00│公開予定 -
町田恵美
01│MAX PLAN 1970-1979 -
港千尋
02│瞬間建築 -
港千尋
01│長い橋 -
関川歩
01│南方以南 the Hidden South -
呂孟恂
00│プロフィール -
町田恵美
00│プロフィール -
関川歩
00│プロフィール -
港千尋
00│プロフィール -
瀬尾夏美
05│ふるさと -
ぬかつくるとこ
05│上木戸工作室 -
辻田美穂子
05│BRIDGE STORY05 -
辻田美穂子
04│BRIDGE STORY04 -
ぬかつくるとこ
04│コイケノオイケ -
瀬尾夏美
04│架空のまち|誰かに旅をしてもらう -
ぬかつくるとこ
03│しょうへいくんのプラバン工場 -
辻田美穂子
03│BRIDGE STORY3 -
瀬尾夏美
03│なくなったまちを訪ねて -
ぬかつくるとこ
02│とだのま -
辻田美穂子
02│BRIDGE STORY02 -
02│掘る形 -
瀬尾夏美
02│山の終戦を訪ねる -
キオ・グリフィス
01│文聞録~其の一 -
辻田美穂子
01│BRIDGE STORY01 -
ぬかつくるとこ
01│「ぬか つくるとこ」とは -
瀬尾夏美
01│陸前高田にて -
01│The Color of Oil -
瀬尾夏美
00│プロフィール -
00│プロフィール -
00│プロフィール -
キオ・グリフィス
00│プロフィール -
辻田美穂子
00│プロフィール -
ぬかつくるとこ
00│プロフィール -
ムーニー・スザンヌ
05│レジリエント・アーティスト -
齋藤彰英
05│《移動すること》構造線と塩の道 ⑤ -
大谷悠
05│現代都市のアジールと「あそび」のクオリティ -
大谷悠
04│都市の「あそび」に集まるひとたち——「日本の家」となかまたち -
舩木翔平
05│新しい日常を創り出すこと -
舩木翔平
04│野菜たちの作り方 -
原亜由美
05│記憶の居場所 -
仲宗根香織
05│小舟で漕いで行く -
太田エマ
04│#IAmaMigrant -
江上賢一郎
05│『流転しつつ根をはること -マレーシア、インドネシアの芸術・文化実践- 』 -
齋藤彰英
04│《移動すること》構造線と塩の道 ④ -
ムーニー・スザンヌ
04│猫の生活:下、上、間、後ろ、向こう -
太田エマ
03│70代以上の女性:どうやって働いてきたのでしょうか? -
江上賢一郎
04│都市の瓦礫から文化をつくる。(韓国) -
仲宗根香織
04│宇宙につながる歴史、光、写真 -
原亜由美
04│リトアニアとハワイ -
大谷悠
03│「公共空間」で「あそぶ」— 小倉城を攻め落とした話 -
ムーニー・スザンヌ
03│都市発展のオルタナティブ・タイムライン -
齋藤彰英
03│《移動すること》構造線と塩の道 ③ -
舩木翔平
03│畑の中の小さなお店から始まる出来事 -
江上賢一郎
03│台南の家族たち -
仲宗根香織
03│傷の想像力 -
原亜由美
03│照らされること -
ムーニー・スザンヌ
02│包含し、守り、分ける、壁 -
齋藤彰英
02│《移動すること》構造線と塩の道 ② -
大谷悠
02│産業遺産を「アート」で「あそぶ」— ドイツの衰退工業都市に「パラダイス」をつくった話 -
舩木翔平
02│街にヤギ -
太田エマ
02│アートとプレカリアート¹ -
原亜由美
02│土地と向き合う -
江上賢一郎
02│Alternative Asia 香港編(後編) -
仲宗根香織
02│生まれ変わる街を想像する力 -
齋藤彰英
01│《移動すること》構造線と塩の道 ① -
大谷悠
01│「空き家」と「あそび」— ライプツィヒ「日本の家」 -
舩木翔平
01│ニュータウンに残された奇跡の農村風景 -
ムーニー・スザンヌ
01│場所から場所へ移動する / As We Travel from Point to Point -
原亜由美
01│夏と記憶の欠片 -
太田エマ
01│パブリックと領域
場所を持つことはパブリックを不可能にするか? -
江上賢一郎
01│Alternative Asia 香港編(前編) -
仲宗根香織
01│秘密のない風景 -
ムーニー・スザンヌ
00│プロフィール -
舩木翔平
00│プロフィール -
大谷悠
00│プロフィール -
齋藤彰英
00│プロフィール -
仲宗根香織
00│プロフィール -
原亜由美
00│プロフィール -
太田エマ
00│プロフィール -
江上賢一郎
00│プロフィール
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22