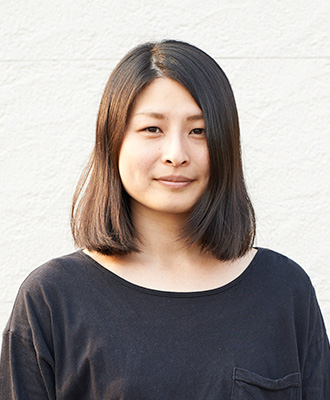
辻田美穂子
Mihoko Tsujita
故郷は文字通り、誰しもが持っている唯一無二の場所です。しかしそれは揺らぐことのない絶対的な存在なのでしょうか。16歳から19歳まで過ごしたオーストラリアでは自分が日本人であることを根本から否定されるような出来事がありました。生まれた大阪という土地で染み付いた風習を恥じ、土地柄はできるだけ隠して過ごしました。一方で、海の向こうから届く祖母からの手紙には、訪れることのできない遠い故郷の思い出が、大事に綴られていました。
他人と共有したい素晴らしい景色も、できれば隠しておきたい事柄も、写真として切り取られた「今」は、在りのままとして等価に写ります。たったひとつの場所を想い続けるということ。根を下ろさずに土地を移ろい暮らすとういうこと。2013年に北海道に移り住んで以来、これらの境界はだんだんと曖昧になりつつあります。日々の暮らしにカメラを持ち込み、全てを一旦並列にすることで、わからなさを解きほぐしていきたいと考えています。
他人と共有したい素晴らしい景色も、できれば隠しておきたい事柄も、写真として切り取られた「今」は、在りのままとして等価に写ります。たったひとつの場所を想い続けるということ。根を下ろさずに土地を移ろい暮らすとういうこと。2013年に北海道に移り住んで以来、これらの境界はだんだんと曖昧になりつつあります。日々の暮らしにカメラを持ち込み、全てを一旦並列にすることで、わからなさを解きほぐしていきたいと考えています。
05 BRIDGE STORY05
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/single-story.php on line 49

まだ日も昇らない暗い雪道は、街灯が反射してキラキラと光り、歩くたびに、キュッキュと鳴く。そんな日の気温はマイナス10度に近いか、更に下回っているんだと感じる。気温が下がれば下がるほど、鳴き声は高くなるので、今日は何度かな、昨日より寒いな、そんなことを考えながら仕事へ行く。広い通りへ出るとすぐ眼下の街にはうっすらと雲海が見える。マイナス20度くらいになると、放射冷却で冷やされた空気が絹の柔らかいベールのようになり、街の上空に浮かぶ。冬至を過ぎたあたりから、日の出の時刻が毎日数分ずつ早くなる。これからどんどん日が長くなるかと思うと、冬はまだ始まったばかりなのにもう春のことを考えてしまう。1分や2分の差はわからないのだが、毎朝決まった時間に家を出ていると、10日分の太陽の高度の移動にはっとする。
2015年の春から、住み込みの季節労働をしている。必要最低限のものだけを段ボール箱1つ分に収めて、北海道内を転々とする。今までも、オーストラリア、アメリカ、東京と住まいを移して来たが、移動には、常に新しい発見と刺激が伴った。2年から3年という短いスパンでの移動を繰り返していたので、巡ってくる季節は、学校や仕事へと出かける毎日の忙しい生活の中に、ふと存在していた。冬の寒さはただ煩わしく、夏の湿度も不快きわまりなかった。その季節がまたやってくるというのは億劫だったが、同じ土地に長くはいないのでほんの少しの我慢ですんだ。ところが北海道に来てから、新しい季節がやってくるのが待ち遠しくてしかたない。重いコートを一枚脱いで、体が軽くなる春。半年もの間雪の下でじっとしている植物たちは、夏が来ると爆発するように生命の色をいっせいに放ち出す。短い夏が過ぎた頃に収穫期を迎える栄養たっぷりの秋野菜たちを堪能していると、ある朝、雪が窓の外の色や音のすべてを包み込み、辺りは凛とする。新しい季節が始まったことを喜び、長らく味わっていない次の季節を楽しみにしながらその時間を終える。そんなことをしている間に、辺りは4度目の雪景色になった。含水率の低い粉雪はとても軽く、枝につもってもすぐに風に飛ばされる。焦げ茶色のものさびしい枯れ木の林に、ふわりさらりとそれらが舞い、いくらか華やぐのを窓から眺めるのが好きだ。
そんな季節を毎日の中で感じられるようになったのは、富良野に来てからだ。ここでの暮らしはナージャがサハリンでしている暮らしとどこか似ている。人々の暮らしと自然がとても近い距離にあったり、街の人同士のつながりが密である。困っていると手を差し伸べてくれるが、幾分かは懐疑的に、そして用心深く見られているというのも感じる。移住者への風当たりが強いのは、その個人に対する誹謗とは限らない。そもそも、オーストラリアで目の当たりにした対アジア人差別は、中国人による空き家の買い占めが原因だった。その地域に暮らす子供たちが優先して入れる進学校の周りの空き家を、まだ小学校にもあがっていない子供が将来通えるようにと、中国本土に暮らしながら購入する人が多数いたのだ。アメリカで聞いたメキシコ人に対する差別の一因も、収入に困った違法移民たちが仕事を占拠してしまうというところにあるという。排他的になるのは、元来人間に備わっている防衛本能かもしれない。生まれてから死ぬまでの間ずっと向き合っていかなければならない紡がれた時間は、その人が向き合うすべての世界だ。そんな自分たちの日常が脅かされるのはすごく怖い。
続けていかなければならない日々と定住することとは、私の中でとても近い意味だった。生活する上での様々な支払いや、近所との付き合いなど、拠点をもつことで自分の行動は制限されると思っていた。それはとても窮屈で、生きづらくなると感じていた。
ある年、住み込みの仕事を急に辞めたことがあった。住んでいる場所もすぐに出て行かなければならない。困って連絡したのが、富良野で両親のように慕っている知り合いだった。困っているんだったらおいでとすぐに呼んでくれたが、そうなった経緯を話しているうちに、「根無し草はどこにも行けない」と言われた。全く意味がわからなかった。根無し草であるからこそ、すぐにどこにでも行けると信じて疑わなかったからだ。「お前に背負っているものはあるのか」そう言われた時に、後頭部を叩かれたような気持ちになった。そんなものは、皆無だからだ。関係を作るということを放棄して、その世界から離脱してしまうことは簡単だ。もうそこに行かなければいい。だけど、必ず後ろめたさが伴う。
オーストラリアで感じた行き場のないどうしようもない悲しみは、「わからない」の渦にのまれたまま、約10年もの間、暗い水底にずっと沈殿していたような気がする。そしてその悲しみはいつしか、どんなことにも向き合う覚悟のない自分自身の後ろめたさとなって自分に取り憑いていた。そういう状況を避け良い状態だけに触れ合って、同じ場所にとどまらないということは、人との関係も続けていくことができない。良い部分はもちろん嫌だなと感じる部分も、向き合わなければいけないのは他人との関わりあいから生まれるものだけではなく、自分自身もだ。それは時間もエネルギーもいることだと思う。だけど、もうこの後ろめたさを見て見ぬ振りしたくない。私はここにいる、と胸をはりたい。
近頃は、近所のスーパーに行くと知っている人にばったり会うことも増えた。「春になったら山菜採りに連れて行ってくださいね」などと言うと「じゃあお互いのしょうゆ漬けを交換しよう」という話になったりする。ひとつの場所に暮らしていても、できることや、周りの人たちと共有する体験が増えていくのが、今はとても新鮮だ。
住所が変わるたびに、祖母からふとしたタイミングで手紙が届く。手紙のやりとりは、オーストラリアにいた頃から10年ほど続いている。内容は、最近でかけた場所や、出会った人、家族のこと、時折季節ごとの樺太時代の思い出も書かれていたりする。ある日の手紙には、「夏の終わりには家族で山へ行って、かごいっぱいのフレップを採ってきて、ジュースやシロップ漬けにしました」と書かれてあった。「フレップ」とはアイヌ語で「赤い実」という意味らしい。サハリンへ初めて行く前からその単語は何度も聞いたことがあり、他の樺太生まれの人たちにとっても故郷を思い出す懐かしい味なのだという。祖母によるとフレップはブルーベリーだそうだ。しかし、ある人によるとそれはこけももだったり黒すぐりだったり、証言はまちまちで、一体「フレップ」が何を指すのかずっとわからないままだった。しかし、もしかすると「フレップ」はベリーの総称なのかもしれないとふと思ったのは、富良野で2度目の夏を迎えた時だった。7月頃からハスカップ、ラズベリー、黒すぐり、山ぶどうと野山のベリーたちが順々に食べごろとなる。「今週末は雨が降るから、その前に急いで採りに行かないとね」などという会話もあちらこちらで聞かれる。同じ亜寒帯に属しているので、植生もよく似ているのだろう。永続的に繰り返す季節の巡りの中にも、発見があると知った。
この春で住み込み生活を終えて2年ぶりに住所を持つ。ナージャや祖母のように、目の前にある日々を肥やしにしながら、ひとつの土地に暮らしてみたい。
2015年の春から、住み込みの季節労働をしている。必要最低限のものだけを段ボール箱1つ分に収めて、北海道内を転々とする。今までも、オーストラリア、アメリカ、東京と住まいを移して来たが、移動には、常に新しい発見と刺激が伴った。2年から3年という短いスパンでの移動を繰り返していたので、巡ってくる季節は、学校や仕事へと出かける毎日の忙しい生活の中に、ふと存在していた。冬の寒さはただ煩わしく、夏の湿度も不快きわまりなかった。その季節がまたやってくるというのは億劫だったが、同じ土地に長くはいないのでほんの少しの我慢ですんだ。ところが北海道に来てから、新しい季節がやってくるのが待ち遠しくてしかたない。重いコートを一枚脱いで、体が軽くなる春。半年もの間雪の下でじっとしている植物たちは、夏が来ると爆発するように生命の色をいっせいに放ち出す。短い夏が過ぎた頃に収穫期を迎える栄養たっぷりの秋野菜たちを堪能していると、ある朝、雪が窓の外の色や音のすべてを包み込み、辺りは凛とする。新しい季節が始まったことを喜び、長らく味わっていない次の季節を楽しみにしながらその時間を終える。そんなことをしている間に、辺りは4度目の雪景色になった。含水率の低い粉雪はとても軽く、枝につもってもすぐに風に飛ばされる。焦げ茶色のものさびしい枯れ木の林に、ふわりさらりとそれらが舞い、いくらか華やぐのを窓から眺めるのが好きだ。
そんな季節を毎日の中で感じられるようになったのは、富良野に来てからだ。ここでの暮らしはナージャがサハリンでしている暮らしとどこか似ている。人々の暮らしと自然がとても近い距離にあったり、街の人同士のつながりが密である。困っていると手を差し伸べてくれるが、幾分かは懐疑的に、そして用心深く見られているというのも感じる。移住者への風当たりが強いのは、その個人に対する誹謗とは限らない。そもそも、オーストラリアで目の当たりにした対アジア人差別は、中国人による空き家の買い占めが原因だった。その地域に暮らす子供たちが優先して入れる進学校の周りの空き家を、まだ小学校にもあがっていない子供が将来通えるようにと、中国本土に暮らしながら購入する人が多数いたのだ。アメリカで聞いたメキシコ人に対する差別の一因も、収入に困った違法移民たちが仕事を占拠してしまうというところにあるという。排他的になるのは、元来人間に備わっている防衛本能かもしれない。生まれてから死ぬまでの間ずっと向き合っていかなければならない紡がれた時間は、その人が向き合うすべての世界だ。そんな自分たちの日常が脅かされるのはすごく怖い。
続けていかなければならない日々と定住することとは、私の中でとても近い意味だった。生活する上での様々な支払いや、近所との付き合いなど、拠点をもつことで自分の行動は制限されると思っていた。それはとても窮屈で、生きづらくなると感じていた。
ある年、住み込みの仕事を急に辞めたことがあった。住んでいる場所もすぐに出て行かなければならない。困って連絡したのが、富良野で両親のように慕っている知り合いだった。困っているんだったらおいでとすぐに呼んでくれたが、そうなった経緯を話しているうちに、「根無し草はどこにも行けない」と言われた。全く意味がわからなかった。根無し草であるからこそ、すぐにどこにでも行けると信じて疑わなかったからだ。「お前に背負っているものはあるのか」そう言われた時に、後頭部を叩かれたような気持ちになった。そんなものは、皆無だからだ。関係を作るということを放棄して、その世界から離脱してしまうことは簡単だ。もうそこに行かなければいい。だけど、必ず後ろめたさが伴う。
オーストラリアで感じた行き場のないどうしようもない悲しみは、「わからない」の渦にのまれたまま、約10年もの間、暗い水底にずっと沈殿していたような気がする。そしてその悲しみはいつしか、どんなことにも向き合う覚悟のない自分自身の後ろめたさとなって自分に取り憑いていた。そういう状況を避け良い状態だけに触れ合って、同じ場所にとどまらないということは、人との関係も続けていくことができない。良い部分はもちろん嫌だなと感じる部分も、向き合わなければいけないのは他人との関わりあいから生まれるものだけではなく、自分自身もだ。それは時間もエネルギーもいることだと思う。だけど、もうこの後ろめたさを見て見ぬ振りしたくない。私はここにいる、と胸をはりたい。
近頃は、近所のスーパーに行くと知っている人にばったり会うことも増えた。「春になったら山菜採りに連れて行ってくださいね」などと言うと「じゃあお互いのしょうゆ漬けを交換しよう」という話になったりする。ひとつの場所に暮らしていても、できることや、周りの人たちと共有する体験が増えていくのが、今はとても新鮮だ。
住所が変わるたびに、祖母からふとしたタイミングで手紙が届く。手紙のやりとりは、オーストラリアにいた頃から10年ほど続いている。内容は、最近でかけた場所や、出会った人、家族のこと、時折季節ごとの樺太時代の思い出も書かれていたりする。ある日の手紙には、「夏の終わりには家族で山へ行って、かごいっぱいのフレップを採ってきて、ジュースやシロップ漬けにしました」と書かれてあった。「フレップ」とはアイヌ語で「赤い実」という意味らしい。サハリンへ初めて行く前からその単語は何度も聞いたことがあり、他の樺太生まれの人たちにとっても故郷を思い出す懐かしい味なのだという。祖母によるとフレップはブルーベリーだそうだ。しかし、ある人によるとそれはこけももだったり黒すぐりだったり、証言はまちまちで、一体「フレップ」が何を指すのかずっとわからないままだった。しかし、もしかすると「フレップ」はベリーの総称なのかもしれないとふと思ったのは、富良野で2度目の夏を迎えた時だった。7月頃からハスカップ、ラズベリー、黒すぐり、山ぶどうと野山のベリーたちが順々に食べごろとなる。「今週末は雨が降るから、その前に急いで採りに行かないとね」などという会話もあちらこちらで聞かれる。同じ亜寒帯に属しているので、植生もよく似ているのだろう。永続的に繰り返す季節の巡りの中にも、発見があると知った。
この春で住み込み生活を終えて2年ぶりに住所を持つ。ナージャや祖母のように、目の前にある日々を肥やしにしながら、ひとつの土地に暮らしてみたい。
記事一覧
-
2020-summer-story
02│8月12日 台湾 -
2020-summer-story
01│8月5日 東京 -
2020-summer-story
00│公開予定 -
町田恵美
01│MAX PLAN 1970-1979 -
港千尋
02│瞬間建築 -
港千尋
01│長い橋 -
関川歩
01│南方以南 the Hidden South -
呂孟恂
00│プロフィール -
町田恵美
00│プロフィール -
関川歩
00│プロフィール -
港千尋
00│プロフィール -
瀬尾夏美
05│ふるさと -
ぬかつくるとこ
05│上木戸工作室 -
辻田美穂子
05│BRIDGE STORY05 -
辻田美穂子
04│BRIDGE STORY04 -
ぬかつくるとこ
04│コイケノオイケ -
瀬尾夏美
04│架空のまち|誰かに旅をしてもらう -
ぬかつくるとこ
03│しょうへいくんのプラバン工場 -
辻田美穂子
03│BRIDGE STORY3 -
瀬尾夏美
03│なくなったまちを訪ねて -
ぬかつくるとこ
02│とだのま -
辻田美穂子
02│BRIDGE STORY02 -
02│掘る形 -
瀬尾夏美
02│山の終戦を訪ねる -
キオ・グリフィス
01│文聞録~其の一 -
辻田美穂子
01│BRIDGE STORY01 -
ぬかつくるとこ
01│「ぬか つくるとこ」とは -
瀬尾夏美
01│陸前高田にて -
01│The Color of Oil -
瀬尾夏美
00│プロフィール -
00│プロフィール -
00│プロフィール -
キオ・グリフィス
00│プロフィール -
辻田美穂子
00│プロフィール -
ぬかつくるとこ
00│プロフィール -
ムーニー・スザンヌ
05│レジリエント・アーティスト -
齋藤彰英
05│《移動すること》構造線と塩の道 ⑤ -
大谷悠
05│現代都市のアジールと「あそび」のクオリティ -
大谷悠
04│都市の「あそび」に集まるひとたち——「日本の家」となかまたち -
舩木翔平
05│新しい日常を創り出すこと -
舩木翔平
04│野菜たちの作り方 -
原亜由美
05│記憶の居場所 -
仲宗根香織
05│小舟で漕いで行く -
太田エマ
04│#IAmaMigrant -
江上賢一郎
05│『流転しつつ根をはること -マレーシア、インドネシアの芸術・文化実践- 』 -
齋藤彰英
04│《移動すること》構造線と塩の道 ④ -
ムーニー・スザンヌ
04│猫の生活:下、上、間、後ろ、向こう -
太田エマ
03│70代以上の女性:どうやって働いてきたのでしょうか? -
江上賢一郎
04│都市の瓦礫から文化をつくる。(韓国) -
仲宗根香織
04│宇宙につながる歴史、光、写真 -
原亜由美
04│リトアニアとハワイ -
大谷悠
03│「公共空間」で「あそぶ」— 小倉城を攻め落とした話 -
ムーニー・スザンヌ
03│都市発展のオルタナティブ・タイムライン -
齋藤彰英
03│《移動すること》構造線と塩の道 ③ -
舩木翔平
03│畑の中の小さなお店から始まる出来事 -
江上賢一郎
03│台南の家族たち -
仲宗根香織
03│傷の想像力 -
原亜由美
03│照らされること -
ムーニー・スザンヌ
02│包含し、守り、分ける、壁 -
齋藤彰英
02│《移動すること》構造線と塩の道 ② -
大谷悠
02│産業遺産を「アート」で「あそぶ」— ドイツの衰退工業都市に「パラダイス」をつくった話 -
舩木翔平
02│街にヤギ -
太田エマ
02│アートとプレカリアート¹ -
原亜由美
02│土地と向き合う -
江上賢一郎
02│Alternative Asia 香港編(後編) -
仲宗根香織
02│生まれ変わる街を想像する力 -
齋藤彰英
01│《移動すること》構造線と塩の道 ① -
大谷悠
01│「空き家」と「あそび」— ライプツィヒ「日本の家」 -
舩木翔平
01│ニュータウンに残された奇跡の農村風景 -
ムーニー・スザンヌ
01│場所から場所へ移動する / As We Travel from Point to Point -
原亜由美
01│夏と記憶の欠片 -
太田エマ
01│パブリックと領域
場所を持つことはパブリックを不可能にするか? -
江上賢一郎
01│Alternative Asia 香港編(前編) -
仲宗根香織
01│秘密のない風景 -
ムーニー・スザンヌ
00│プロフィール -
舩木翔平
00│プロフィール -
大谷悠
00│プロフィール -
齋藤彰英
00│プロフィール -
仲宗根香織
00│プロフィール -
原亜由美
00│プロフィール -
太田エマ
00│プロフィール -
江上賢一郎
00│プロフィール
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22
Warning: array_pop() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 19
Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/users/2/abi0707/web/a-b-i.info/wp/wp-content/themes/abi/sidebar.php on line 22